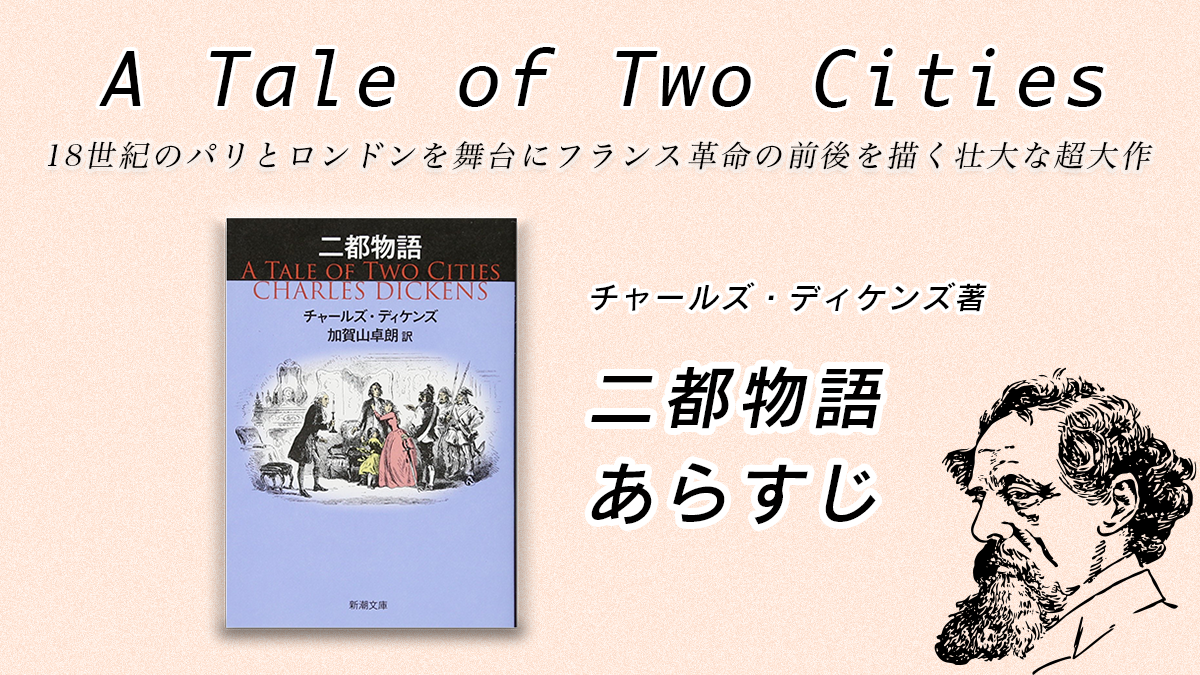この記事は下記のような方におすすめです。
- 「二都物語」の読みどころを分かりやすく解説してほしい!
- 「二都物語」のどこを読めばいいのか(読みどころ・POINT)
- 「二都物語」を読んだ人の生の感想。
二都物語ってどんな小説?
イギリスの作家チャールズ・ディケンズが、48歳の時に書いた作品。(初版は1859年刊)
物語としては階級闘争フランス革命を背景に、その時代を生きる人々を、法廷劇や殺人、革命の動乱、裏工作などを交えて壮大なスケールで描いています。
ディケンズの後期の作品であり、いわゆる歴史もの。作品はトーマス・カーライルの『フランス革命史』を書かれたと言われています。
まるで映画のようなストーリー展開で、当時映画という文化がないのにもかかわらず、それを小説で作り上げるのはホント天才としかいえません。全世界で2億部突破の大ロングセラー。
二都物語の書かれた背景や経緯とは?
二都物語は、フランス革命の真っ只中にあるフランスとイギリスを舞台に描かれます。
フランス革命は、1789年のバスチーユ監獄襲撃に端を発して、フランス全土を巻き込んだ市民による革命です。
革命の背景としては、ジョン・ロックを代表とする啓蒙主義思想(社会は平等である)が市民階級に広がるとともに、絶対君主制のもと特権的な立ち位置にいた国王や貴族に対する市民たちの怒りによるものです。
市民たちは共和制(話し合いによって物事を決めようとする)を実現するために、「自由、平等、友愛」というスローガンのもと、有名な国王のルイ16世、そしてその妃のマリー・アントワネットが処刑することで、フランス王政と封建的な身分制度を打ち倒します。
二都物語はこうしたフランス革命の混乱を、その渦中で激しく運動していた民衆の立場で描いている作品です。
二都物語の「二都」とは?
タイトルである二都物語の「二都」とは何でしょうか?
それは、小説の舞台となるフランス・パリ、イギリス・ロンドンのことを指します。
物語は、全てこの二都を行ったり来たりが続きます。
二都物語のテーマは?
二都物語はフランス革命を舞台に、その時代を生きる市民や貴族の姿をありありと描いています。
それは明るい面というよりは、貴族の横暴だったり、封建制度の闇、革命志士(市民)たちのいき過ぎた処刑など、フランス革命前後の18世紀当時のフランスにおける社会悪・暗い部分を描いたテーマがあります。
血に飢える群衆、暴力的な革命、煌めくギロチンの刃に取り囲まれる中、愛する者を持つ一人の貴族は、進み続ける。復讐に襲われ死刑台へと引摺られる。だがもう一つの愛が彼を救う。嫉妬を超越した愛、それは夢物語でありだからこそ美しい。
『二都物語』を読む上で意識するべきところは、「貴族階級」の「市民階級」VS構造です。
そして貴族が『虐げの対象であった市民たち』から虐げられる、という反転図式も面白いところ。
作中前半では、貴族が市民を虫けらのように扱う様子が描かれます。
でも作中後半では、その関係性が反転して、市民たちが貴族を虫けら的な対象として、断頭台へと上げて処刑し続けます。※回転砥石を用いて「革命の敵」=「貴族」を虐殺する場面をはじめ恐怖感と抑圧感に満ち、無辜の犠牲者を生んでいる。まさに死に導く黒い悪魔のよう。
反転する力動は、封建制度による日常の虐げに対する、市民たちの「膨らんだ憎悪」がエネルギー源になっているのです。
憎悪のエネルギーはとにかく凄まじく破壊的で、貴族に向けて「処刑=死」という恐ろしい形で反転していきます。
怒りの放出はどこまでいってもやまず、フランスから逃げ出した亡命貴族さえも捕まえて処刑へと導いていきます。
物語後半に、市民が貴族たちを次から次へと死へ導いていくのは、そうした抑圧されたエネルギーが行き場を持たないままに放出されていくのを描いています。
二都物語を表すキーワードは?
僕は二都物語を読んで、作品に対して下記のような印象を持ちました。
- フランス革命を壮大なスケールで描かれる歴史もの
- 18世紀のフランスにおける民衆と貴族の関係性
- シドニー・カートンの波乱の人生を通じて見えてくる、力動的な“運命”
- 市民による革命の“火”、集団の行動性
二都物語のあらすじ簡単要約
時代は18世紀後半の1775〜1792年で歴史的に有名なフランス革命が起こる前後。
舞台はロンドンとパリ。物語は1775年から始まる。
フランスのバスティーユ監獄に、無実の罪で18年投獄されていたアレクサンドル・マネット医師。
彼の友人であり、ロンドンのテルソン銀行に勤める銀行家ジャーヴィス・ローリーは、マネット医師が牢獄から、とき放たれたことを聞く。
彼はマネット医師娘のルーシーを連れ、アンシャン=レジームが支配するフランス・パリへと向かう。(娘ルーシーは、幼い時にフランスで父親と母親をなくしていると聞かされていた)
マネット医師は酒店を営むドファルジュ夫妻が経営する酒場でかくまわれていた。無事彼を救出した二人は、イギリスへと連れ帰る。
その途上、船上で、フランス人のチャールズ・ダーニーと出会う。チャールズはフランスの貴族なのだが、パリで行われる悪政に嫌気をさして、名をかえて亡命イギリスに亡命してきたのだ。
ただ彼はイギリス政府からスパイ容疑をかけられる。だがチャールズと瓜二つの弁護士で、人生に絶望したシドニー・カートンに助けられる。
また投獄されていた当時のおそろしい記憶に蝕まれているマネット医師は、娘ルーシーとチャールズが手厚く介抱するなかで、徐々に精神が安定していく。その過程の中で、チャールズとルーシーは愛をはぐみ、晴れて二人は夫婦となる。そして愛すべき子供も生まれる。
ときを同じくしてフランス。
貴族階級による横暴に対して、市民階級は憎しみや憎悪、怒りに燃えたぎっていた。そしてサン・デヴレモンド侯爵が、名もない一市民に殺されたのを機として、暴徒と化した民衆の蜂起がおこる。
フランス革命だ!
市民たちは死の使者となって、貴族階級を根絶やしにしようと、次々と貴族を捉えて、断頭台(ギロチン)へ送り込む。
ダーニーはフランス・パリで起きている状況を、侯爵の召使ガベルとその娘マリー(マリー・ヴェルシニ)から知らされる。彼は貴族に仕えていたという理由から民衆に捉えられており、彼を救いに単身フランスに戻る。
だが民衆の怒りは、当然貴族出身・サン・テヴレモン侯爵の甥であるチャールズにも降り、捕らえられて革命裁判の結果、処刑さることに。
絶望に瀕したルーシーとマネット医師たちの元に現れたのは、シドニー・カートン。彼はある秘策を思いつくーー。
フランス革命を背景に、マネット家とチャールズたちが革命の大波に翻弄されていく壮大なスペクタクル。
二都物語の主な登場人物紹介
二都物語に登場する登場人物たちを紹介します。
チャールズ・ダーネイ
本作の主人公。
フランスの侯爵の息子だが、パリで繰り広げられる悪政にしびれを切らしてイギリス・ロンドンへ亡命。
亡命国イギリスでは国を売るものとして怪しまれて裁判にかけられるが、シドニー・カートンによって助けられる。
ルーシー・マネット
マネット医師の娘。
物語のはじめは17歳になる直前。
銀行員ローリーに連れられてパリに渡り、すでに亡きものと思っていた父親と感動の再会を果たす。白髪の髪形。
ローリーにイギリスに連れてこられて、銀行が管理していたマネット医師の財産をなんとかやりくりしてこれまで生きてきたのであった。
ジャーヴィス・ローリー
イギリスのテルソン銀行の銀行員で働く。
歳をとっているが、若者に負けないくらい活発に働く。
紳士として非常に優しい性格。テルソン銀行パリの支店で20年ほど。
働いていた彼は、お得意様だったルーシーの父でフランス人のマシュー・マネットと親しかったのです。
カツラの紳士。実務家。
マネット医師を心の底からの友として扱い、多くの場面で彼を支え、その娘も支える人物。
アレクサンドル・マネット
無実の罪で18年間バスティーユ牢獄に。
非常な知識と経験がある人物。
一時は精神を靴磨き。
現実的に強いストレスが働くと靴づくりのベンチに座り道具を叩き、ひたすらを靴を作る。それは頭の中の混乱を鎮めるために、己の手作業に集中させることで忘れる逃避の一種。あるいはこころの防衛である。靴づくりをするとき、己の記憶無くなる。
ルーシが結婚したときには、生きる希望を失い、9日間、茫然自失の体でひたすら靴を作り続けた。しかし友ローリー氏の賢明な支援もあり、それ以後立ち直りを見せて、最終的には靴づくりの道具をすべて火の中に捨てた。
章「意見」にその詳細がある。
記憶が戻ってからも、靴作りの道具は手放せず。チャールズがエブレモンド一族だとわかった時は、ショックからまた一時的に記憶を失い、靴作りをはじめてしまう。
シドニー・カートン
人生に絶望した放蕩無頼の弁護士。むとんちゃくな生活を続けているが有能な弁護士で、マネット医師を救う。そこで出会ったルーシーに恋をするが、己に対する引け目を感じて、心に素直にならずに恋心を隠す。
一度ルーシーに恋心を伝えるが、同情を買われただけで終わる。ダーネイと顔が似ている。
エルネスト・ドファルジュ
フランスのパリ・サンタントワーヌで夫婦で経営すワイン酒場の店主。かつてはマネット医師の使用人をしていた。その縁故で、バステーユ監獄から開放された後、彼を匿っていた。
ドファルジュ夫婦はフランス革命で指導者的な役割を演じ、酒場には多くの革命児が集まる。革命の同志達をジャックと呼び合う。
テレーズ・ドファルジュ
エルネスト・ドファルジュの妻。
姉がサン・テウレモンド侯爵兄弟に殺されて、貴族階級に恨みを抱いている。
いつも編み物に従事しているのだが、実は酒場で聞かれる噂や情報を聞き、復讐する名前や特徴を網目と模様で編み込んでいる。
沈着な性格で肝が座った女。北欧神話のウルズ(編む者・運命の三女神の長女)のニュアンスがある。
「復習や報復には長い時間がかかる」が有名。
彼女の最後は呆気ないものであり、ミス・プロスとの戦いの最中に不運にも、銃が暴発し惨めに死ぬ。
ジョン・バーサッド
ミス・プロスの弟でイギリス人。1793年時点ではフランス側のスパイになっている。
一度ドファルジュ夫妻のもとに訪れて、フランスに反旗を翻す動向を探りに来た。そのときに、チャールズ・ダーネイが、サン・テウレモンド侯爵の甥であることを告げる
歳は四十前後で、背は約五フィート九インチ。
眼は黒、黒髪で肌も浅黒く、全体として男前だが、顔は細長くて血色が悪い。 鷲鼻が左の頬のほうに少しゆがんでいるので、悪人めいて見える。
姉ミス・プロスの金をくすねて以降、失踪する。
サン・テヴレモンド侯爵
フランスの貴族。横暴であり、残忍。チャールズ・ダーネイの叔父(父親の双子の弟)
民衆を馬車で轢き殺し、フランス革命の怒りを膨らませる。
最期は、領民によってベッドの上で殺される。
ストライヴァー
シドニー・カートンの同僚で法律家。
ルーシーによる恋心があると、思い違いで求婚する。
たが実務家であるローリーによって「やめておけ」とアドバイスされてやめる。(このやりとりは面白い!)
ギャベル
ダーネイの使用人。ダーネイに忠実で、領地を管理している。
暴動のときに村人の手につかまり、アベイ監獄にかくまわれる。
二都物語の読みどころ・感想解説
ここでは、二都物語でどういった部分を意識して読んだほうがいいか、読みどころを解説しますね。
マネット医師は、なぜ投獄されたの?
マネット医師は18年もの間バスティーユ牢獄に収容されていた、と物語の始まりに語られます。
ではなぜマネット医師は投獄されたのでしょうか。その理由は、あるフランス貴族の秘事を知った(厳密には目撃した)ためです。
そのフランス貴族というのは、物語の最後に明かされるのですが、チャールズ・ダーネイの叔父サン・テヴレモンド侯爵です。
そして秘事とは、サン・テヴレモンド侯爵が、テレーズ・ドファルジュの姉とその夫たちを惨殺した過去です。
実はそれをマネット医師が目撃したのです。
さらに言えば、テレーズ・ドファルジュは当時幼児であって、姉たちが侯爵の手によって惨殺される場面を、見えない場所から見ていました。
人は個ではなく、群衆化すると
二都物語でディケンズは群集心理というものを巧みに描いています。
有名な心理学者フロイトは、集団について下記のように表現しています。
集団の中に個人が寄り集まると、個人的な抑制がすべて脱落して、太古の遺産として個人の中にまどろんでいた残酷で血なまぐさい破壊的な本能がすべて目ざまされて、自由な衝動の満足に駆り立てる
フランス革命における市民たちはまさに当てはまることで、群衆がより集まると、個人の力は相殺・抑制されて、一種の狂気的な情動にまとわれたよって動くということ。
例えば、フランス貴族を裁くための、チャールズを裁く裁判においては、群集を非個性的でありながら一つの人格を持ったような描き方をしています。そこでは個の哀れみや理性は失われており、集団が寄り集まると抑制のタガがはずれて、残酷で
煽動された
フランス革命期の異常な心理状態
フランス革命は歴史的に見ても異常な事態を取り扱っています。
二都物語の面白さは、そういった歴史を引き起こした登場人物たちの異常な人間状態を匠に描いていること。
それは例えば、先導された集団の陥る“狂信性”、“悪魔的な乱舞”、御祭性
ギロチンで次々と貴族の首が跳ね飛ばされるのですが、その恐怖凶器は一種の娯楽性が出て、首をふきどばす一撃は、怒り・憎悪とともに歓喜・
踊り続ける人々は祝祭の伝統を受け継ぎ、抑圧された 生命力を狂気じみた行為の中で発散させ、すべての関係を破棄して、現存する社会システ ムから解放されようとする。しかし、革命輪舞では、典型的なカーニヴァルの様相が見ら れても、人々が打破すべき体制は既に崩壊している。
革命空間に限らず特殊な状況においても、誰もが個人的な判断を下 すことよりも集団的な行為に身を任せる傾向にあることを示している。
フランス革命であった時代は、下記の客観描写も非常に面白い描写です。
何があったのかは、長いことルーシーには知らされなかった。囚われて身を守るすべもない一万一千人の老若男女が民衆に殺されたこと、その四日間は残虐行為の闇に包まれ、彼女のまわりの空気も死臭で汚染されていたことをルーシーが知ったのはずっとあとで、フランスから遠く離れていたときだった。当時の彼女にわかってい たのは、いくつかの監獄が襲われ、囚われた政治犯全員が危険にさらされ、群衆に引きずり出されて殺された者もいるということだけだった。
暴力!恐怖!のオンパレード。映画を思わせる描写!
二都物語でぜひ意識して読んで欲しいのが、映画のような描写です。
ディケンズといえば、割とユーモア性だったり、家族の温かい描写だったりが多いのが特徴。でも二都物語はテイストが異なり、まるでノンフィクション作品のように、かなり濃度が濃いめで、非常に緊迫した様子を描くシーンがたくさん出てきます。
例えば「第七章 都会における貴族モンセーニュール」で描かれるチャールズ・ダーネイの叔父サン・テヴレモンドが、パリの労働者の子供を馬車ではね殺すシーン。
これは当時の貴族がいかに平民を虫けらのように扱っていたのかが分かるのですが、一巻きの映画のような描き方で、めちゃくちゃ迫真があります。
烈しいがらがらがたがたという音を立てながら、今の時代では了解するのに容易ではないほどの不人情な思いやりのなさで、その馬車は幾つもの街をまっしぐらに駈け抜け、幾つもの街角を飛ぶように走り曲って行き、女たちはその前で悲鳴をあげるし、男たちは互に掴まったり子供たちをその通路の外へ掴み出したりした。とうとう、一つの飲用泉の近くのある街角のところへ走りかかった時に、馬車の車輪の一つが気持悪くちょっとがたつき、数多の声があっと大きな叫び声をあげ、馬どもは後脚で立ったり後脚で跳び上ったりした。
「何の故障か?」と馬車に乗っている方が、静かに顔を外に出して見ながら、言った。 寝帽ナイトキャップをかぶった一人の脊の高い男が馬の脚の間から包みのようなものを抱え上げ、それを飲用泉の台石の上に置いて、泥土のところへ坐って、その上に覆いかぶさりながら野獣のように咆えていた。
「御免下さりませ、侯爵さま!」と襤褸を著た柔順な一人の男が言った。「子供でござります。」 「どうしてあの男はあのような厭わしい声を立てているのじゃ? あの男の子供なのか?」 「失礼でござりますが、侯爵さま、――可哀そうに、――さようでござります。」 ーーー
脊の高い男が突然地面から起き上って、馬車をめがけて走って来た時、侯爵閣下は一瞬剣のつかにはっと手をかけた。
「殺された!」とその男は、両腕をぐっと頭上に差し伸ばし、彼をじっと見つめながら、気違いじみた自暴自棄の様子で、言った。「死んじゃった!」
人々は周りに寄り集って、侯爵閣下を眺めた。彼を眺めている多くの眼には、熱心に注意していることの他ほかには、どんな意味も現れてはいなかった。目に見えるほどの威嚇や憤怒はなかった。また人々は何も言いはしなかった。あの最初の叫び声をあげた後には、彼等は黙ってしまったし、そのままずっと黙っていた。ーー
侯爵閣下は、あたかも彼等がほんの穴から出て来た鼠ででもあるかのように、彼等一同をじろりと眺めた。
彼は財布を取り出した。 「お前ら平民どもが、」と彼が言った。「自分の体や子供たちに気をつけていることが出来んというのは、わしにはどうも不思議なことじゃがのう。お前たちの中の誰か一人はいつでも必ず邪魔になるところにいる。お前たちがこれまでにわしの馬にどれだけの害を加えたかわしにもわからぬくらいじゃ。そら! それをあの男にやれ。」
あるいは絵のような迫真の描写に驚きます。(この近辺にある他にもワインの酒樽が荷台から転げ落ちて、道路に広がった赤葡萄酒に群がる貧しい人々の描写も生々しいです。)
また圧巻な描写は、パリでは革命志士たちによる「フランス革命の準備」が進められ、それが徐々に近づいていくるのを「足音」によって表現しています。そして貴族の横暴に対する反感・憎悪が爆発し、憎悪のエネルギーはすさまじい力となってノートルダムを民衆の怒涛の波も襲撃、そして解放と続き、次から次へと革命の描写がつづく。
その言葉の溢れかえり方は凄まじい。火災やら、人の吊し上げやら、喜びと狂気の叫び声などーー。
それはまるで死のカーニバルのようで、血祭りに挙げられる貴族たちは残酷にも死へと導かれていきます。
革命の緊迫感と同時に、動き始めたら止まらない動的な様子を、ディケンズの素晴らしい筆致で表現されています。
それらはすべて貴族の横暴に対する反感なんですが、積りに積もった憎悪のエネルギーは最後にはすさまじい革命という嵐になってうねっていくんですね。
テレーズ・ドファルジュという女
二都物語で最も印象に残る登場人物は、テレーズ・ドファルジュ。
フランス革命における『暴力』の化身として、多くの貴族たちを断頭台へ送り込み、死へと導く死神的な立ち位置です。
彼女は暴徒と化す民衆全体を体現しています。
彼女の復讐に邁進する姿は、まるで復讐の女神エリーニュスのよう。
彼女はつねに棒針編みに没頭しているのですが、それは「復讐すべき貴族たちの名前を編み込んでいる。
作中で、彼女を表現した下記の言葉。
『冷酷無比で無慈悲な鉄の女』という印象が浮かび上がってきます。
このころ、時代のせいで怖ろしい容姿に変わった女は大勢いた。が、そのなかでも、 いま通りを歩いているこの無慈悲な女(テレーズ・ドファルジュ)ほど怖れられた存在はなかった。強靭で怖いもの知らずの性格、抜け目のなさ、用意周到な気構え、固い決意、そして本人に強い意志と敵愾心を与えるだけでなく、まわりの人間にも本能的にそれを感じさせる類の美しさを具えていた。時代が混乱すれば、状況にかかわらずこういう女が力を持つものだが、子供のころから暗い悪の観念と、上流階級に対する根深い憎悪を植えつけられ ていた夫人は、この機に雌トラに進化した。この女には憐憫の情がまったくなかった。 かつてはその美徳があったとしても、いまや完全になくなっていた。無実の男が先祖の罪をかぶせられて死のうと、夫人にとってはなんでもないことだ った。彼女はその男ではなく、先祖の兄弟を見ていた。男の妻が寡婦になろうと、娘 が孤児になろうと、どうでもいい。それでも罰としては不充分だった。彼らは不倶戴天の敵であり、獲物なのだから、生きる権利などない。夫人に命乞いをしても無駄だった。自分に対してすらまったく憐れみを感じないのだ。もし夫人が数多の市街戦のどれかで倒れたとしても、自分を憐れんだりはしないだろう。
ちなみにテレーズの過去は、作品の後半にでてきますが、とても悲しく、不幸に満ちています。
なぜ彼女がここまで貴族を恨むようになったのかの理由がわかります。
幼い頃、彼女の姉がチャールズの叔父と父親(サント=エブルモント侯爵たち)によって殺されます。
だからこそ、サント=エブルモント侯爵家は永遠の憎悪の対象であり、先祖末代まで呪うという、憎しみに駆られているのです。
そしてその憎悪の対象は、チャールズだけでなく、その血筋と関わる周りの人々(ルーシー、マネット医師)にまでも向けられます。
ここまで強烈なキャラクターを作り上げたディケンズはやはりすごいです。
そうしてテレーズを影で支えるのが夫のエルネスト・ドファルジュ。
彼もまた革命で指導的役割を演じる一方で、マネット医師の使用人をやっていたことから、ルーシーへの同情心からテレーズに彼らの命を助けてやるように主張する。
ところがテレーズ・ドファルジュは怒りの炎に包まれているため、夫の言葉を却下します。
カートンの自己犠牲の意味することは?
優れた才能がありながら、酒に溺れさせてその才能を浪費するロンドンの弁護士シドニー・カートン。
彼は二都物語の裏主人公として容姿は瓜二つだが、性格的には真逆。なのでチャールズが光とするならば、その反面の”影”のように、暗く対称的に描かれています。一般的に、二人は分身関係があると言われています。
ただ「灰の塊」だった彼も最後には、英雄的な自己犠牲によって復活を果たします。
それは革命裁判で処刑されるはずだったチャールズ・ダーネイの代わりに、自分の命を犠牲にする、愛の自己犠牲です。それは酒に溺れた生活の償いの意味もあると思いますが、愛するルーシーへ捧げる、愛による自己犠牲なのです。
僕はこの自己犠牲はによる象徴は、キリスト教的な「復活」だと思っています。
例えば下記の言葉ははっきりとそれを示しています。
「我は復活であり命である、と主は言われた。我を信じるものは死んでも生きる。生きて我を信じる者は死することはない」
彼はこれまで酒に溺れ、死んだように生きてきたのですが、ルーシーという愛すべき信じるべきものができて、彼女のために自己犠牲をすることで、「再び生きる機会」を与えられたのです。
この世では命を捧げて、復活をはたすという考えは、キリスト教の殉教者を思わせます。
ちなみに革命の先頭に立ったマダム・ドファルジュの死は銃の暴発による「つまらない死」である一方、カートンの死は「美しさ」や「重々しい荘厳さ」を持っています。
マネット医師とルーシーの父子関係
マネット医師は18年もの間、バスティーユ監獄に収容されています。
彼は過酷な囚人生活のなかで、精神を病み、現実から逃避するように、時に心が彷徨ってしまうことがあります。
そんな父親を献身的に支えようとするルーシーはまるで聖母のよう。
父のために本を読んであげたり、散歩にでかけたり。
父娘のなんともいえない、親和的な関係は読んでいて心地が良い。
個人的には、章「ある夜」の、スズカケの木の下で、チャールズと結婚について父娘が話し合うシーンは印象的。
特にマネット医師が監獄生活を思い出して、「想像の子供を思い浮かべる」の回想は痛々しい。
「あれをごらん」 ボーヴェの医師は月を指差した。 「私は監獄の窓からあの月を見た。 あの光に耐えられなかった。月を見て、自分が失ったものにあの光が降り注ぐと考えるだけでつらくてたまらず、 監獄の壁に頭を打ちつけた。 何をする気も起きない暗い気分であの月を見て、満月に横線と縦線を引いていったら何本入るだろうということ しか考えられなかった」 いつもの内向きな黙考の態度で月を見上げて、つけ加えた。 「それがどちらも二十本だったのを覚えているよ。 二十本目は押し入れるのがむずか おぼしかった」
そのそばで寄り添って傾聴しているルーシーは、とても心を痛めている。
夜、スズカケの影の中で、月光に照らされる二人は、芸術的な趣があります。