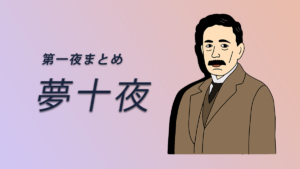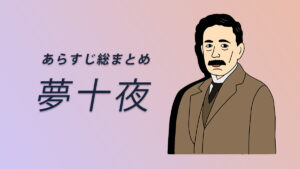この記事は下記のような方におすすめですよ。
- 「道草」の読みどころを分かりやすく解説してほしい!
- 「道草」を読む前に簡単にあらすじを知りたい!
- 「道草」を読む際にどこをポイントにして読むめばいいかを知りたい!(読みどころ・POINT)
生きるというのは、決して楽ではありません。
苦悩をあげればキリがないですが、というのを抱えながら生きていきます。
特に「人間の血縁関係」というのは非常に重い繋がりです。
その固い繋がりに終生苦しめられたのが漱石であり、道草は苦悩の根本である実体験がベースになった作品です。
今回はそんな「道草」を初心者の方にも分かりやすく説明していきますね。
たかりょーの読書のすすめ!
- 読みながら、気になった部分はメモを取っておく
- 読んだ後になぜ気になったのか、何をどう感じたのかを書く
2点を意識しながら読むことでより深く読書ができますよ!
道草ってどんな小説?【概要】
道草は大正4(1915)年6月から9月にかけて全102回『朝日新聞』で連載された小説です。
漱石は翌大正5年に胃潰瘍のために死去しますから、その前年に書かれた作品といえます。
ちなみに死去した時には未完の大作となった『明暗』執筆中であったため、実際完成作品としては『道草』が最後となります。
道草の成立した背景まとめ
道草は、漱石が死ぬ直前であったときに、自らの過去・出生を振り返って書いた作品と言われています。(←この点は後述で詳しく解説します!)
過去とは教師をしながら我輩は猫であるや坊ちゃんを書いていた頃の出来事です。
実体験がベースになっているため、例えば、御住(主人公の妻)のヒステリーは漱石の実妻の鏡子夫人も抱えていたなど複数リンクするところがあります。(親類からお金の無心をされるという漱石のお馴染みの話も出てきます)
道草のテーマは?【何を伝えたい作品なのか】
道草は家族の物語を通じて描かれる「人間の苦悩」について書かれた小説だと思っています。
なので作品はとにかく暗いです。
「我輩や猫である」のようなユーモアもなければ、「坊っちゃん」のように痛快さもないです。「三四郎」のような甘酸っぱい青春物語でもありません。
読んでいて淡々と日常生活が描写されているため、つまらないと感じる読者が大半かもしれません。
ただその描写を通じて、僕たちには「永遠に片のつかない苦悩」と言うのを感じます。
苦悩とは例えば、親類との縁もあれば、お金の問題、あるいは人間の性、もっと深くいえば人間存在そのもの、これらから発生するともいえます。
「世の中に片付くなんてものはんどありしない」という名言があるのですが、
chidspotの「人間って」の歌詞にある「人間ってこんなんもんだろ」って感じない限りは、ちょっと心が病むかもしれません。
『道草』を表すキーワードとは?
- 家庭生活
- 半自叙伝
- 親類という重い絆
- 夫婦生活の過酷さ
- ヒステリー
- トラウマ
道草のあらすじ簡単要約
健三が遠い所から帰って来て駒込の奥に所帯を持ったのは東京を出てから何年目になるだろう。彼は故郷の土を踏む珍らしさのうちに一種の淋し味さえ感じた。
の冒頭で始まる本作。
舞台は東京の本郷区駒込千駄木町。
小雨降るある時、健三は勤め帰りに家の近所をウロウロしているうらぶれた老人(帽子を被らない老人)を見かける。
それは十五前に別れたはずの、かつての養父島田であった。(健三は幼年時代、養子にやられていたのである)
幼い頃、養子に出された健三は生家に戻って以来、20年も養父島田とは疎遠となっていた。
現在の健三は、長い留学生活を終えて帰国後、大学の教師としての職を得て、妻の御住とふたりの娘の4人で家庭生活を送っていた。
とはいえその家庭生活は平和とはいえるものではなく、何事も論理を振り回す健三と、奔放な性格と神経症気味の妻とは幾度も激しくぶつかり、夫婦仲はしっくりきていなかった。
健三からすると、細君は積極的に夫に向かって胸を開く女でなく、妻の身勝手な性格に時おりヒステリーの発作を出すこともあり、
さらに学問一筋の生活を希求し、しかも、大長編小説に取りかかっている健三はただでさえ時間が足りないの に、日常の様々な些事が彼の頭を悩まします。
叔父島田が近づいてきた目的は、落ちぶれており一角の人物(大学教授)になった健三からお金をせびりにきたのである。
彼は最初、姿を見せるだけであったが徐々にエスカレート。
島田はまるで過去の亡霊かのように、健三のもとにたびたびあらわれます。(←これは逆ハムレットともいえます)
養子という形でありながらも、一度は親子の縁を結んだ仲。
近いものが困っているときは助けてくれと、理論武装をしてお金をせびってくる島田。
そんな健三を無下に断ることができずにいた。
実際、島田の出現は単にお金の問題ではなかった。
昔養子として預けられていた幼い頃の記憶がまるで原風景となって蘇ってきた。
そうして彼を追い回す方ととなる。
さらに健三のもとには島田だけでなく、島田の先妻お常、姉お夏、妻お住の父といった、健三と過去に関係のあった親類たちがたち現れ、お金の無心にうようよとたかり始めます。(まるで悪魔のようです!!)
夫婦生活も危機的な状況に陥りながらも、最後には解決として島田に手切金として百円を渡し絶縁することを確約させる。
最後にやっと事が片付いた喜ぶ御住に向かって、健三は「世の中に片付くなんてものはんどありしない」と吐き捨てる。
永遠に 「片付かない」日常の苦悩を描いた自伝小説ともいえる家族の物語。
道草の登場人物
道草の登場人物を教えて欲しい。
道草は登場人物の関係性が非常に重要です。なぜならその繋がり(縁故)による苦悩を暴き立てるからです。物語の中心は大学教師の健三です。そして家庭生活に叔父が登場することから物語が始まります。その妻御住との関係や周りの親類たちとの関係も暴かれるようになります。
健三
主人公36歳。(漱石がモデルになっていると言われている)
東京大学を卒業後に、海外留学から帰国後大学の教授の職を得る。研究もしている。
娘は3人いる(うち一人は物語の中で生まれる)
性格は無神経で頑固、高慢ちき。世間慣れしておらず、内気な様子。
妻を教養・学問のない人間と低く見て軽蔑しており、論理的にやり込めようとする。
御住を軽蔑しており、馬鹿呼ばわりすることも。
紳士の典型である「山高帽をかぶっている」ので社会的な地位は上の方。
守銭奴のように日々働くがそれ以外は書斎にこもって自分の読みたい本を読み、執筆している。
月収は百二、三十円。
御住(おすみ)/健三の妻
官僚の娘であり、自由な空気の中で育った背景もあって自由奔放な性格。
夫が始終書斎にこもり、打ち解けた話もせず、一人で思いを隠すことがあるので、不信感を抱いている
子供に対して愛情を注ぐ女性である反面、時折ヒステリーをおこし、精神がおかしくなりうわ言をもらす。
そのようなヒステリーは、健三の胸に暗い不安の影を投げてやまない。
島田/健三の養父
健三が3歳から7歳まで引き取っていた。 数十年ぶりに健三の元に現れてお金を無心しにくる。
過去に未亡人のお藤と不倫して、その後妻とは離婚する。
健三の父とは喧嘩をして義絶している。
御常(おつね)/健三の養母
健三に嫌な記憶を呼び起こす養母。御縫に島田を奪われる形で離婚。
感情を転移するかのように健三へ強い愛情を植え付けた。(夫への復讐の意味合いもあったのか?)
彼女も島田同じくまた二十数年ぶり健三の元にやってきて健三にお金を無心しにきた。
御藤(おふじ)島田の後妻
島田の後妻となった美人な女性。
御縫(おぬい)
柴野の嫁で御藤の連れ子。
すらりとかっこの良い姿、面長でまつ毛の多い切長な目。
健三より年が一つ上であり、一度は健三・健三の兄との婚約の話もあった。
不治の病気(脊髄病)で死去。
柴野
御縫の旦那で軍人。
肩の張った色黒い男、目鼻立ちからして立派な人。
高崎から遠く西の方面へ転任。(師団から旅団のある中国へ)
大酒飲みも影響してか家計はそこまで豊かではない。
御住(おすみ)の父親
元官僚。(過去には貴族院の候補にも)
その過去があってから健三より遥かに世間馴れている。
無作法な物言いをする愚劣な健三の高慢なところを嫌う。
ただ今はすっかりと零落している身である。
借金を依頼する人がおらず、義理の息子である健三に保証人になってもらうために彼の元に訪れる。
御夏(おなつ)
健三の異母姉。よくしゃべる女性。
喘息持ちでかなり体が弱っている。(三日も四日も寝ずに食べずにを続けることも)
かなり衰えて痩せ細っている。
ひとところにおさまる事ができずに、家の中をウロウロとうろき回っている。
字が書けず、教養も乏しい女性。
道草の読みどころ解説【引っ掛かりポイント】
帽子を被らない老人の意味は?
本作で養父の島田の特徴として「帽子を被らない」というのが殊更強調されています。
彼の頭にこの間途中で会った帽子を被らない男の影がすぐひらめいた。
それはなぜでしょうか。
僕の予想では主人公健三と島田の、今の地位の対比を描いているのだと思います。
現在でもエルメスのバックやら大きそうな時計をはめているとか。
身につけているものによって、その人の地位がなんとなく予想できますが、そういった効果を狙っているのでしょうか。
主人公は山高帽をかぶっており、養父は帽子を被らないのは困窮の様、地位の低さを象徴しています。
道草の名文(印象に残った言葉・場面・セリフ)
劇烈な雰囲気が記憶に残る
ある晩健三がふと眼を覚まして見ると、夫婦は彼の傍ではげしく罵ののしり合っていた。出来事は彼に取って突然であった。彼は泣き出した。その翌晩も彼は同じ争いの声で熟睡を破られた。彼はまた泣いた。こうした騒がしい夜が幾つとなく重なって行くに連れて、二人の罵る声は次第に高まって来た。しまいには双方とも手を出し始めた。打つ音、踏む音、叫ぶ音が、小さな彼の心を恐ろしがらせた。最初彼が泣き出すとやんだ二人の喧嘩が、今では寐ようが覚めようが、彼に用捨なく進行するようになった・・・やがて御常は(幼い)健三に事実を話して聞かせた。その話によると、**彼女は世の中で一番の善人であった。これに反して島田は大変な悪ものであった。**しかし最も悪いのは御藤んであった。「あいつが」とか「あの女が」とかいう言葉を使うとき、御常は口惜しくって堪まらないという顔付をした。幼稚な健三の頭では何のために、ついぞ見馴みなれないこの光景が、毎夜深更に起るのか、まるで解釈出来なかった。彼はただそれを嫌った。道徳も理非も持たない彼に、自然はただそれを嫌うように教えたのである。 「あいつは讐だよ。御母さんにも御前にも讐だよ。骨を粉にしても仇討かたきうちをしなくっちゃ」
まるでその場の息遣いが聞こえてくるかのような描写です。また幼い頃の健三の記憶にへばりつく、”忘れ慣れない光景”としての意味もあって、島田はおそらくその場面を何度も頭の中で繰り返されたのであろうというのがわかります。太字で記載したところは、感情的な女性が発言しそうな自分よがりな論理ですね。
窒息感がつらい(拭いきれない血縁との関係)
彼(健三)は途々自分の仕事について考えた。その仕事は決して自分の思い通りに進行していなかった。一歩目的へ近付くと、目的はまた一歩彼から遠ざかって行った。 彼はまた彼の細君の事を考えた。その当時強烈であった彼女のヒステリーは、自然と軽くなった今でも、彼の胸になお暗い不安の影を投げてやまなかった。彼はまたその細君の里の事を考えた。経済上の圧迫が家庭を襲おうとしているらしい気配が、船に乗った時の鈍い動揺を彼の精神に与える種となった。彼はまた自分の姉と兄と、それから島田の事も一所に纏まとめて考えなければならなかった。凡が頽廃の影であり凋落の色であるうちに、血と肉と歴史とで結び付けられた自分をも併せて考えなければならなかった。
人間はある可能性があり、それにむかって進まなければ生きている心地がしないのでしょう。
実際、血縁の人間というのは、支えてやるべき存在でありながら、健三の足ばかり引っ張っています。
ここから学べるのは、「人間は窒息感を感じることで、己自身の可能性をも閉じる」
複雑な家庭関係があるから、このような暗い思考になっていると思うのですが