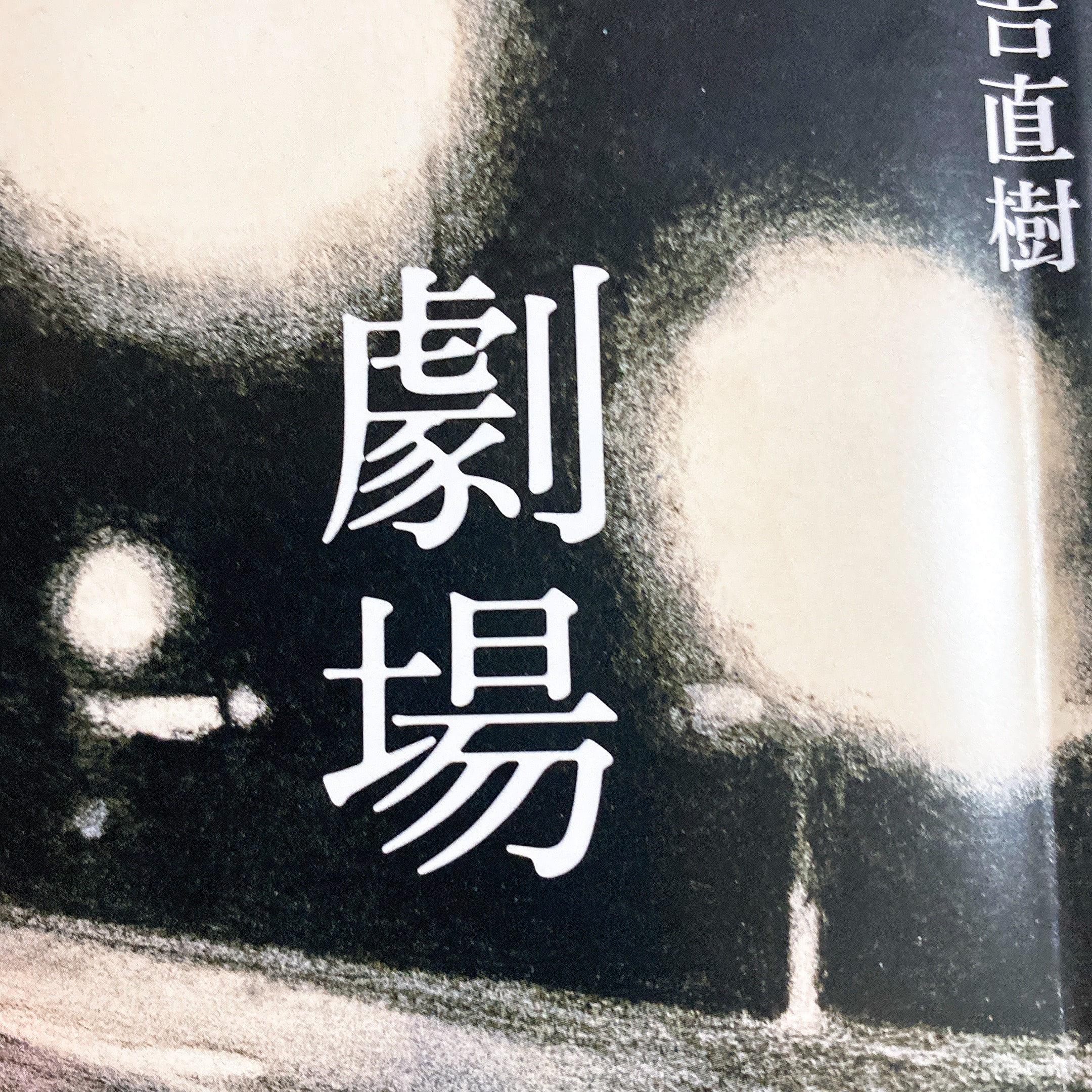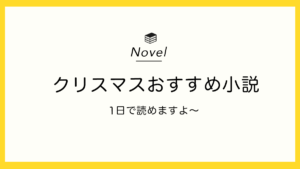・小説『劇場』の詳細のあらすじが分かる
・小説『劇場』読むべきポイントが分かる
先日、僕はこのようなツイートをしました。
劇場 #読了
久しぶりに衝撃を受けた小説人間ほど愚かな存在はないけど、又吉さんはそれを知りつつ、”人間は愚かだ”と描いてない
愚かさは”痛みの感情”以外に学ぶ術はなく、劇場はその痛みを痛烈に感じる
ただ愚かさを包む”優しさ”も丁寧に描いてるからすごい😊#読書好きと繋がりたい #読書記録 pic.twitter.com/s13Pk8X2kD
— たかりょー|読書大好き・映画大好き・音楽大好き (@RyoooooTaka) April 12, 2020
ずっと読みたい、読みたいと思っていて、とうとう又吉さんの劇場を読みました。
結論、面白すぎて半日くらいでグワ!!って脳フル回転させて、一気に読んじゃいましたよww
人間の嫌な部分をめちゃくちゃ露骨に描いて、なんかヒヤッとさせられました。
又吉さんは正直、芸人をしてる作家っていう次元じゃないですね。
もう日本のなかでも作家又吉直樹だなぽいな〜と思いました。
さて今回は「劇場」のあらすじを丁寧に解説していきますね。
劇場の主要登場人物
永田(ながた)
本作の主人公。売れない劇作家。自意識が非常に高く、人に対する疑心が強い。エゴイズムを内部に抱えている。沙希と出会うことで変わる
沙希(さき)
女優になる為青森県から上京。親の勧めもあり服飾大学に通いながら女優を目指している。優しさの化け物。永田の芸術性を心の底から信じてやまない、健気なヒロイン。
野原(のはら)
永田とは中学からの同級生。劇団「オロカ」をともに立ち上げる
青山(青山)
「オロカ」の元劇団員。永田の演劇や姿勢に反発して退団。のちに永田に文筆の仕事を依頼する
小峰
永田と同時代の劇作家。周囲からは天才扱いされており、永田の嫉妬の対象になる
あらすじ①.永田と沙希の出会い
売れない劇作家永田は、劇団を主宰するために上京してきたのだが、全く売れません。
永田という人物を一言で特徴付けるなら、膨らみすぎた異常な自意識をもっていること。
人の目線を異常に気をしたり、自分の才能が認められないことへの反発心、のうのうと生きている人の嘲笑い 、かと言えば自分より才能のある人間を嫉妬したり。鬱屈した毎日を過ごしている
8月の午後のこと。
永田は新宿から代々木体育館に沿う道を当てもなく歩いていると、ある画廊にたどり着きます。
ガラス越しに画廊内部の絵画を覗いていると、隣に若い女性いるのに気づきます。
パッと見た印象は、健康的で明るい。
思わず永田は、沙希をじっと見つめます。
幽霊のような風体の永田に、長々と眺められた沙希は、危険を察知したのか、足早に逃げ出します。
しかし永田は、すぐに彼女の背中を追いかけます。
そして変人扱い、当然、犯罪者と認識されてるかもと思いつつ、「靴同じやな」と声をかけます。(下手くそなナンパ
をしたわけです)
この時、永田は沙希に対して、ある感情をいただきます。
それは
・生まれた時から彼女のことを知っている
・いつも彼女の人生を近くで見守ってきた
という非現実的ですが、おそらく親近感と名付けられるものです。
これまで人と深く関わりあうことを避けていた永田にとっては非常に珍しい、だが素直な感情でした。
沙希は警戒心を最初は強めていましたが、「お金に困っているのだ」というふうに早合点し、二人は近くのカフェに行くことになります。
「さっきすごく怖かったですよ。迫ってきたしたよね」
と笑い話にしながら、お互いのことを話し合う。
永田は中学生の頃から演劇に興味を持ち出して、大阪から上京して劇団を立ち上げた話を
沙希は青森出身で、女優を目指すために上京してきた。親の服飾店の手伝いができるかもという服飾専門の大学で学んでいる話を
永田はあまり自分から積極的に喋りませんが、沙希は勝手に一人で話題を見つけてはクスクス笑い出すというふうに、先ほど奇妙なナンパをされたことなど気にしていない様子です。
永田にとって沙希は「声を聞いているだけで嬉しい」ような存在であり、何が面白いのかわからないがよく笑う女性であり
そこで沙希は青森から上京してきたこと
そして女優を目指していたということを知る。
演劇を始めたきっかけを話したりと、二人の交流を深めていky
結成して三年になる。
あらすじ②.売れない劇団「おろか」
永田は友達の野原とともに立ち上げた劇団「おろか」を立ち上げました。
おろかの脚本は全て自らの手で書いていますが、客からの受けは悪いです。
なぜなら、大衆に迎合するような演劇は鼻から興味がなく、あくまで「感情が様式をなぎ倒すような自分の演劇」=“芸術性”を突き詰めた作品ばかり作っていたからです。
大衆とは、そこまで大きく芸術性を求めるものではありません。
尖ったものが受け入れられるのは、ほんの一握り。
当然7割・8割の聴衆にとって、そんな芸術性云々などは「バカな・わからない」と遠ざけられてしまう。
永田も実はそんな芸術性を求めた演劇と大衆が求める演劇との間で、「売れない日々」が続いていたのでした。
そんな事情もあって、下北沢にある八幡湯二階の下北ファインホールという“下の下”の舞台で公演するのがやっと。
(もちろん下北沢駅前劇場で公演することは不可能に近かった)
また自分含めて5人しかいない数少ない劇団のメンバー2人が、永田に大きく反発して、「変なことをして、動員が減ることを「おろかってる」っていうらしいですよ」と自分の劇団を揶揄して笑い、劇団を辞めてしまいます。
あらすじ③.永田と沙希のデート
永田は沙希をデートに誘います。
「明日、渋谷に家具を見にいきます。もし、暇やったらついてきてくれませんか」
渋谷の西武百貨店あたりで午後5時に待ち合わせます。
永田は人嫌いですが沙希とはどこか「つながる」部分を感じており、
渋谷の家具は定休日か休み。
二人はやることもなく、歩き続けます。
沙希は理想的な速度で歩いてくれた。
二人は何をするわけでもなく、互いの感覚を確かめ合うような会話をしながら、その日のデートは終わります。
デートを境にして二人は急速に中を深めていきます。
またその頃、他の劇団から作品執筆を依頼されて、「その日」を書き上げる事ができます。
演劇
その日を書き上げた永田は伊藤に見せると「ええやん」という感想。
また沙希にも脚本を見せると「読んだよ」「すごい感動した」と真っ赤な目をさせながら言います。
永田にとって、作品の良し悪しを、涙を流すか・流さないかで決めるのは、永田的には考えられないのですが、沙希は、涙を感動の物差しにはしません。
そして永田は沙希に頼みます。
「これな、下北の駅前劇場でやるねんけど、この女役、沙希ちゃんやってくれへんか」
最初自分には無理だよと断りますが、沙希ちゃんに演じてもらいたいとしっかりと説明し、同意を得ます。
初日こそ客足はそこそこだったが、沙希の演技力によって、プロデューサー・観客含めて、上々の評判を得ます。ただ同業者からの批判はあります。
当の沙希といえば、手放しに永田の劇を褒めます。
周りの人間からすれば、永田の作品は「悪くはないが良くもない」くらいのレベルですから、沙希は浮いた存在に見えてしまい
下北の駅前劇場でのある程度の成功をおさめてからというもの、劇団「おろか」の注目度は少しだけ集めます。
定員80名程度の劇場で公演をする事ができるようになります。
とはいえ、下北の駅前劇場で「劇をする」には経費の問題でおろか主催ではできずじまい
もちろん収入が劇的に上がるわけでもなく、反対に稽古する日が増えたということもあって、これまで続けていたバイトもやめてしまいます。
そして家賃を払うことも難しくなり、とうとうアパートを出ることになります。
あらすじ④.沙希の家に転がり込む
永田はアパートを出てから、沙希の家に転がり込みます。
沙希の家に住むことで、生きていくに必要なお金がほとんど入らなくなった
家賃も光熱費も食費も全て沙希がもったからです。(永田はそもそも単発の日雇いをする程度で、これといった稼ぎがほぼありません)
とはいえ、沙希は学生ですから、アパートの家賃は彼女が払うのではなく、彼女の親が払っていました。
例えば、食料に関しても定期的に実家ら届くといったような。
こういった状況を永田本人は、惨めであることは自覚しています。
そもそも自意識が異常に高い彼ですから、一種のメタ認知はしっかりとできているわけで、「俺はこのままでいいのか」「馬鹿げている生活をしているものだ」といった『自己の浅ましさ』は感じていたに違いません。
とはいえ”脚本だけに人生を捧げたい”、“観客の心をえぐるような作品を書き上げ、脚本家として売れる”という夢を叶えるためには、『痛ましい生活がなければどうしようもないだろう』という、自己肯定をするのです。
とはいえ、それはあくまで自分の置かれている事実を隠す方便や隠蔽行為にすぎず、自分の現状と真っ正面から向き合うのを先延ばしにしているだけだったのですが、、、
まともに働くわけでもなく、「俺は芸術性を極めるんだ!」という大義名分に溺れなあがら、昼までゴロゴロと眠り、気持ちが乗ったら、脚本を書くという、まさに何を生み出さない非生産的な生活を続け、干物男になったわけです。
あらすじ⑤.沙希と永田の確執
永田はあくまで芸術を志し、自分の演劇が世間に認められることを求めています。
そのためとあれば、一般的な生活を捨ててもいいし、必要ないとも思っています。
誰かに好かれようともしなければ、
例えば美味しいご飯を食べる、いいところに住む、結婚をする等
かたや沙希は女優を志して上京してきたのですが、普通の幸せも求めている
周りの人間なら誰しもが望む、夢の暮らしというものへの期待はあったわけです。
例えばディズニーランドに行きたいし。富士急ハイランドにも行きたい
つまり、平穏な日常というものを望んでいたのです。
互いにそれを感じながらもあえて言葉に出さない。
これを確執というと大げさかもしれませんが、確実に二人が将来を考えられる恋人として成立するには大きな壁になっていたことは間違いありません。
あらすじ⑥.ふたりの同棲生活
上記のような状況があったんですが、永田と沙希は同居を続けていきます。
永田は、沙希と共演した演劇が、ある程度の評価を受けたことで、脚本家としての仕事が増えます。
ところが公演をかさねれば重ねるほど、バイトをする時間がなくなり、当然、お金が入ってきません。
つまり、ますます沙希におんぶに抱っこの城田となります。
そして沙希は大学卒業後します。
彼女は東京の洋服屋に勤める。そして自分と永田を支えるために夜は居酒屋でアルバイトをするという並行生活をはじめます。
一方で永田は相変わらず非生産的で、芸術云々のことばかり考えていました。
永田は芸術という大義名分をかざしながら、その実態は沙希に寄りかかって支えられていたのでした。
あらすじ⑦小峰というライバル
小説では、永田の嫉妬心を煽る登場人物が現れます。
その名も小峰。
小峰は直接、永田とは絡んでいないのですが、友達の野原に誘われて見にいった「まだ死んでないよ」という公演で、彼の作・演出を手がけた劇に思わず感動し、圧倒的な才能を目の前にして、驚きと焦燥感に囚われるのです。
それに小峰は、永田と同年代の演劇人です。
彼は永田と比較にならないほど周りから高く評価されているおり、強烈な憧れと嫉妬の感情を彼に抱くようになります。
たしかに永田は、沙希とともに演じた劇により、自分が主催する舞台の客足は伸びていた。
ところが「まだ死んでいないよ」のように、この劇団でないといけないまで演劇ファンの心を掴んでいるわけではなかったのです。
「もしかして自分は、小峰よりも才能がないかもしれない」
この劣等感に苛まれ、「世間的に評価されるものなら、俺のように芸術性を求めるものと違う」というふうな数多くの自己肯定を行うのでした。
それは目を背ける現実逃避にすぎなかったのですが、、、
あらすじ⑧.青山からライターの仕事を紹介。一人で暮らすことに
そんなある時、劇団「おろか」をやめた元劇団員の青山から久しぶりに連絡がありました。
「まだ死んでいない」の公演でたまたま永田を見かけたのでした。
「おろか」を退団するまで、自己主張なく、どちらかというと魅力が希薄だった彼女は、現在、演劇と併行して、彼女自身文筆業を行なっています。
そんな彼女から「そうそう、それで永田さんは文章をかく仕事とかどう思っていますか?」
と永田に、記事執筆の依頼を持ちかける。
記事と言ってもエッセイやコラムなどではなく、東京のスポットを取材してアップするネット記事でした。
永田は日雇い労働に比べたら、書くという仕事の方が自分に合っている、仕事を許諾するのでした。
あらすじ⑨.沙希の家を出て一人暮らしを始める
ライターの仕事をちょくちょく請け負うようになったものの、永田は稼いだ金をほとんど自分のために使っていました。
そしてある日、沙希の家を出ることにしました。
小峰という圧倒的な存在感、世間的に天才と呼ばれる価値に対して、焦燥感を覚えるようになり、自分は余裕を捨てて、もっと演劇に打ち込む時間を割かなければならないと考えたのでした。
そして演劇に身も心も捧げようと考えていた永田にとり、優しさや思いやりの塊、自分の弱さを抱きかかえ支えてくれる沙希の存在から離れなけれなならないと考えたのです。
「仕事のためなら仕方ないね。永くんが頑張れるように応援するよ」
そして永田は高円寺のアパートで一人暮らしをすることになったのです。
とはいえ、沙希と別れるということもできない弱さがある永田。
お酒を飲んで酔った時には、沙希の顔が見たくなり、彼女の家に行くのでした。
沙希は優しさの塊ですから、永田を笑って受け入れてくれるのです。
とはいえ小峰という存在への嫉妬心は、日に日に高まっていくばかりです。
そんなある日、沙希の働く居酒屋にきている小峰が事実を知ります。
バイト先に「田所」という劇団員がいて、その関係で小峰が居酒屋にやってきたのです。
また青山が原因となって、永田は自分が居酒屋で笑い者にされていると勘違いし、沙希を罵倒することもありました。
こういった事情により、沙希のアパートにいくことは少なくなりました。
そして沙希からメールが定期的に届くこともありましたが、彼女の前で自分の弱さを怒りという形で表明したことに恥ずかしさを覚えて、返信もすることもなくなるのです。
ただお酒によって気が大きくなった時には、無性に彼女に会いたくなり、合鍵で部屋にはいり、ベットに潜り込むのだった。
とはいえ、朝目がさめると惨めさに襲われてしまい、自分の情けさに恐ろしさを感じるのでした。
こんな日々を繰り返しているうちに、とうとう沙希は
「わたし、お人形さんじゃないよ」
と彼に向かっていうのでした。
自分は沙希の近くにいるのが本来の居場所だと感じている永田でしたが、芸術というもの、そして自己の才能というものを信じきっていたため、安住することを恐れていた、あるいは避けていたのです。
なんと自意識が高い人物でしょう!
そして沙希は夜中に会いにいくと家を空けている時がたまにあり、家にいても彼女自身が酒に溺れていることが多くなったのです。
あらすじ⑨.沙希との喧嘩
青山という人物が、この物語を大きく展開させます。
青山は、よく沙希と「まだ死んでいない」の劇団員と飲むようになったり、あるいは沙希を連れ出して、小峰の演劇に連れていったりするようになります。
この行為に耐えきれないのが、永田でした。
ある日、その不満が爆発して、沙希を責め立てるのでした。
「青山と一緒にその劇団観に行かれへんの俺がいやかなと思わんかったんか」
もう八つ当たりですよね。
「芝居くらい観にいってもいいでしょ別に」
「おもろなかったやろ」
「すっごい、おもしろかったよ!」と先が大きな声をだす。
「殺したろか!」と隣の住人に足して大声を張り上げます。
「永くんおかしいよ」
「そんなん最初からやん」
「わたしもうすぐ27歳になるんだよ、地元の友達はみんな結婚してさ。わたしだけだよ、こんなの」
沙希は大泣きしながら、自分が「真っ当な普通の人間である」ことを必死で伝えるのでした。
あらすじ⑩.沙希を苦しめる永田
沙希は確実に出会った頃に比べて、変化していった。
例えば、ちょっとしたことにすぐにクスと笑うような子だったのに、思いつめたような表情をすることが多くなりました。
そして、毎晩のように酒を飲むようになってもいました。
彼女が変わってしまったのは、永田自身にあることに本人も気づいていました。
永田は道化のようにふざけるようになります。
死に物狂いでふざけるのです。
なぜなら、自分は愚かであること、情けないことを沙希にそして、自分自身に知らしめるためでした。
じゃあ永田は沙希と別れればいいのですが、それを許さないわけです。
というのも、永田にとって沙希は、現実とつながる
もし沙希との縁が切れてしまったら、自分は”本当に愚かであり、落ちこぼれ”になることが決定されてしまうからです。
彼女はあくまで永田を褒めてくれて、一瞬でも芸術という束縛から解放してくれる存在です。
だからこそ、永田は沙希を手放したくなかったのです。
めちゃくちゃワガママですよね。
自分の心の安定を手にする、自分が落ちこぼれにならないように沙希を利用しているのですから。
そして沙希にとっても
別れることを許さなかった。
あらすじ11.永田と沙希の別れ
そしてとうとうその日がきます。
それまで大切な話があるというメールが送られ、その後、「これからのこと」というメールが送られてきます。
いやな予感がしかしないから永田は返信せずに放置しています。
永田は永田で沙希に「何してんの?」と送りますが、いつもなら返してくれるはずなの返信がありません。
そして永田は沙希が働いている居酒屋に向かいます。
店の電気が消えると一人の男性が中から出てきます。
「田所」という男です。
彼に話を聞くと、沙希はとっくに仕事を上がって、店の店長の家にいっていると聞かされます。
いやな予感がします。
彼は店長の家に向かいます
店長のマンションの前には沙希の自転車が置かれています。
自転車のベルを一度鳴らします。もう一度鳴らし、その次もならし、最後には続けてなんども鳴らします。
するとマンションの窓が開きます。
沙希の姿と後ろに黒い影。
階段の降りる音が鳴り響くと次の瞬間には張り詰めた顔の沙希がやってくる。
「何してんねん、帰ろか」
沙希の自転車の後ろに乗せて、帰ります。
彼は安心できる沙希を乗せて、自宅に帰ります。
沙希に向かって、沙希といることがどれだけ幸せなのか、沙希の優しさに自分はどれほど救われたのか。
文脈も考えられず無秩序に吐き出される言葉は、無意味な言葉に聞こえるかもしれませんが、それは彼の胸の中で巣食って意味にならない言葉たちでした。
あらすじ12.東京を出る
沙希は居酒屋バイトをやめ、洋服屋も辞める。
そして家に閉じこもりがちになり、昔の活発な面影はありません。
永田は自身が沙希を確実に追い詰めたことを知っています。
彼はあくまで沙希のそばに寄り添いながら、
しかし精神的に沙希は落ちていき、抑鬱状態となり、夜飲む酒の量も日に日に増えていきます。
当然周囲からみれば永田の沙希への振る舞いが、彼女をとことん追い詰め苦しめていることがわかります。
店長の家にいたのも、彼と浮気をしたとこかではなく、沙希の相談にのっていただけでした。
青木は沙希と別れるべきだと言います。
とはいえ永田にとって、沙希は大げさにいえば自身の片われのような存在。
自分という存在を認め、行いの正しさを信頼し、弱さを受け入れ、守ってくれる存在。
沙希は永田以上に、永田自身の存在を気遣っているのです。
でも沙希はある日永田に言います。
「私、もう東京駄目かもしれない」
酩酊状態で、、、
沙希をこのような状態に追い込んだのは、自分自身であり、沙希はおそらく東京=永田から逃れたかったのです。
良い意味でも悪い意味でも、沙希にとって永田という存在はあまりにも大きかったわけです。
そして沙希は東京に荷物を置いたまま、青森の実家に帰ります。
沙希との関係はこれからどうなるのか、とうの二人には分からないまま。
ネタバレ結末.かなわない夢を語る永田【道化になる永田】
永田は沙希が戻ってきてくれると思っていたが、沙希はやはり東京で暮らすのを諦めます。
実家で心を癒して、徐々に復調してくると、地元の会社で働くことにしたのです。
そして沙希は東京に荷物をまとめるために、戻ってきます。
永田は沙希がいつでも戻ってこれるように彼女の家賃を支払い、いつでも戻ってこれるようにしていたのですが、、、
沙希のアパートへ荷物を整理しにいった時、そこに数多くの懐かしい思い出の品が出てきました。
永田宛の沙希の手紙、劇場公演のチラシ、小道具として使った猿の奇妙なお面、、、
そこには過去の香りが充溢し、
そして永田が手に取ったのは、沙希と一緒に下北沢で公演をした時に脚本です。
あるページに沙希の手による「永くんすげえ」という言葉。
沙希はいつでも永田の味方であり、支え続けてくれる大切な存在だったのです。
・・・
そして夏も過ぎ去り、秋のある日。
沙希は東京にやってきます。
久しぶりに会う沙希は東京で苦しめられた時とは違って、顔色も良くなり、渋谷を歩き、久しぶりの東京を楽しげに満喫している様子。
最後のシーン。
沙希のアパートにきたふたり。
永田は、沙希と一緒に、ある程度の成功をおさめた脚本を手に持っている。
「なんでふざけてんの?なんか私にいうことないの?」と脚本のセリフを読み上げます。
すると、セリフのなかに、あくまでも演じるという様子を崩さず、沙希に対して、自身の想いを嘘偽りなくぶつけます。
いつも現実ではふざけている自身を隠すことばかりしていた永田だったが、トランプの裏表のように、演じるというなかでは“本音”を入れるにです。
「それにしても君に迷惑ばかりかけた。」
沙希もセリフではない素直な気持ちを
「あなたとなんか一緒にいられないよ」
「なんで?」
「いられるわけないよ。昔は貧乏でも好きだったけど、いつまでたっても、なんにも変わらないじゃん。でも変わったらもっといやだよ。だから仕方ないよ」
沙希はわかっていたわけです。
彼と過ごしていくうちに、永田には才能がなかったことを。
でもそんな永田を本気で応援したい気持ちはあるし、諦めない彼を好きだったことを。
「勝手に年とって焦って変わったのはわたしの方だからさ」
ネタバレ、最後の名シーンです。
「演劇にできることは、すべて現実でもできるねん」
という前置きの元、おそらく、“一生叶えられないであろう物語”を沙希に語ります。
現実でもほんとうに起こるかのように、、、
以下まま引用します。
沙希ちゃんは実家に帰る。そこで働きながら元気になる。今も元気やけど、もっとってことな。ほんで俺は演劇を続けて、飛躍的な成長を遂げてな、、、いっぱいお金を稼げるかもしれへん。そしたらないっぱい美味しいもの食べに行くことができる、、、沙希ちゃんはウニが好きやから、ウニをどんぶり山盛りにして食べ続けたら良いよ、、、特急列車にのって温泉に以降。海が見える露天風呂に入って朝焼けを見よう
沙希は泣きながら言います。
「ごめんね」
このごめんねは何を意味するのでしょうか。
「ごめんね、私は永田くんとはもう無理だよ」なのか「ごめんね、私のせいでごめんね」ということなのか。
永田は言います。
「一番会いたい人に会いに行く。こんな当たり前のことが、なんでできへんかったんやろな。」
沙希は嗚咽を繰り返しながら、鳴き続けます。
そして、永田は変な猿のお面をかぶり、まるでピエロのような道化となり「ばあああああ」と何度も言います。
「ばあああああ」
「ばあああああ」
こんなどうしようもない永田を沙希は見て、泣きながら、最後に“笑う”のです。
小説『劇場』の読むべきポイント・感想まとめ
それでは以下にて『劇場』の読むべきポイント・感想をまとめていきますね。
感想01.自分には芸術性がないことを薄々気づいている
永田はうっすら自分に才能がないことを気づいているのでは?と思います。
でも彼はそれを認めることができないから、理論武装したり、自身をあえて追い込むような言動をしたりしているんですよね。
さて永田を特徴付けるのは、強烈な劣等感情です。
世間への嫉妬(世間に迎合しない態度は、自分はそうはなれないからこその衝動感情)や自身と同じ土俵に立つ人間を片っ端から罵る等
たとえば、好きな人が他の人と遊んでるのをみて、嫉妬する場合は、怒りの感情は相手に向かってるのですが、自分に自信がない、自分に魅力がないというのを暗に認めているわけなのです。
永田の場合もそうですよね
自分の演劇はすごいものだと思ってる
でも売れないし、悪い評価もあるし
それらが自信喪失につながり、鬱屈とした感情の吐口として、他人の嫉妬という感情に転換される
これは強い自意識をもつ永田であれば、より強烈な感情として発現するわけなんです。
とはいえ、永田ほど自分の感情に正直になってる人はいないというわけなので、人間の感情を赤裸々に出しているとも言えます
だからこそ人に嫌われてもなんともない
感想02.悪魔的な優しさをもつ紗希
ヒロインである紗希。
彼女は一見、ただの優しさ彼女にみえますが、紗希の優しさは異常です。
永田はエゴイズムの塊であり、世間からは認められない、疎ましがられる存在です。
しかし紗希は永田の才能を心の底から信頼して、永田を徹底的に守ろうとします。
だがそれは永田を苦しめます
なぜなら、世間的に認められていないということを武器にして、納得する芸術を追求したいのに、紗希の無邪気さ・優しさが、永田を芸術に人生を捧げる=モンスターになることを妨げるからです。
実際に(紗希の)無邪気さに救われるとこがあったが、少しでも別のことで心に不安があると無性に神経が昂ぶることがあった。その感覚が腹の底に沈殿すると、自然と表情が強張り、身体に力が入る。そうなるたびに小さなことに拘泥する自分自身のことを、せこくて醜い生き物のように感じてしまう。それでも気持ちは収まらず、執拗に沙希を責めたくなるのだった。P96
つまり、永田にとって紗希は安寧の地でありながら、自己を苦しめ責めさいなむ、存在として
つまり紗希は優しさという正義を振り回し、紗希から幸福を与えられれば与えられるほど、彼の存在意義を否定される様な気がするのです。
自分の居場所が少しずつ紗希よってうばわれる
だが奪われることに自分は心地よさを感じてしまう。
その心地よさは芸術以外の道、つまり世間一般の幸福の道を歩むのであれば心地よくなります。
しかし永田が進みたい道、芸術の道においては、邪魔なだけです。
永田は自己と他者紗希の間でせめぎ合い、どちらともつかずに時間を消耗し切っているわけです。
そして永田は自身の矛盾を痛烈に感じているからこそ、紗希をときに攻め、ときに優しくし、かと言って別れるか結婚するかを決めきれずにいる
とても中途半端な位置に置かれてしまうのです。
つまり紗希は意図せず、自分の悪魔的な優しさ=おそらく心理学的には全てを飲み込む母性ともいえます。よって、結果的に永田という大切にしたい人を苦しめているのです
とはいえ紗希はそのことがわからないからこそ、こわいのです。
無意識にしてしまっている点で、言葉をキツくいえば、罪なのです。