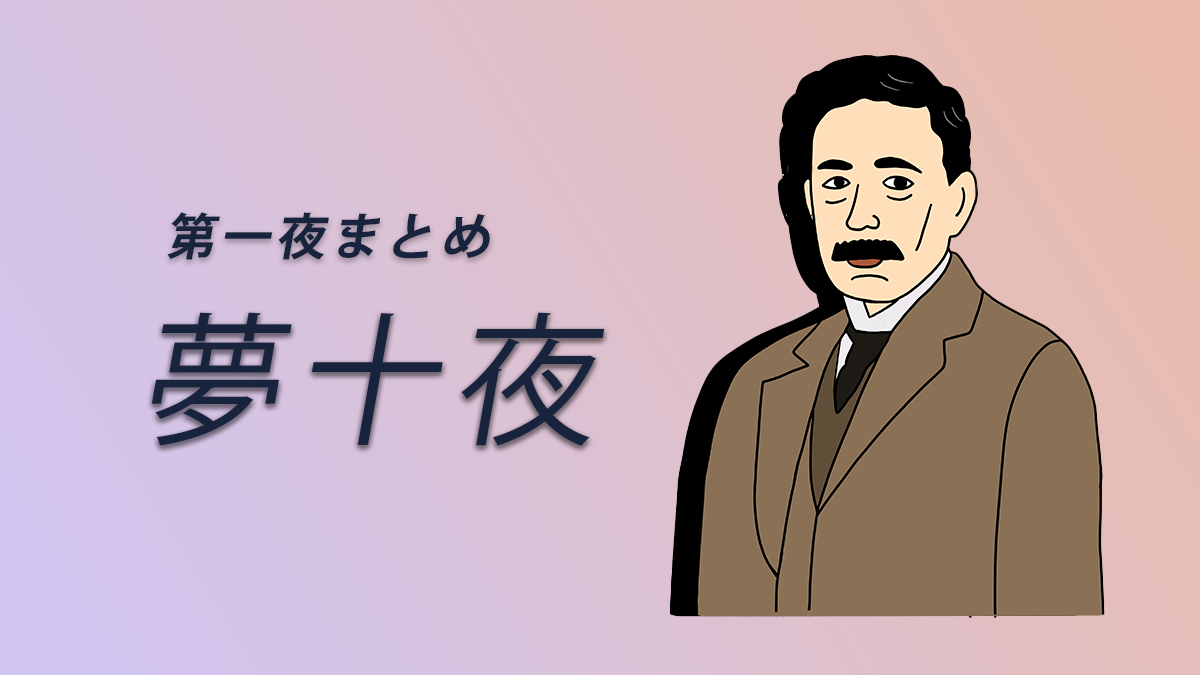もしあなたが女に「百年待っててください、また逢いにきますから」といわれたらどうですか?待ちますか?
自分の願いを成就させるためだと言ってもそんな長い期間待つなんてできませんよね。
でも「第一夜」の語り手である「自分」は待ち続けます。
なぜ待ち続けたのか?永遠の愛か?それとも何かを成就させるためか。
King Gnuのカメレオンを聞きながら読みたいような、そんな儚い物語です。
「夢十夜」とは何か?「第一夜」の立ち位置は?
『夢十夜』は、漱石が専属作家として、入社した朝日新聞時代に書かれた小品。
東西両「朝日新聞」に1908(明治41)年7月25日~8月12日まで、毎日一話ずつ掲載され、1910(明治43)年5月、春陽堂刊の小品集「四篇」に収録されました。
第一夜は、夢十夜の中でも幻想色が非常に強く、特に人気が高く、多くの評論が残されている章です。

「第一夜」のあらすじ
「死んだら、埋めて下さい。 大きな真珠貝って、 そうして天から落ちて来るの破片標に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。また逢いに来ますから」
「自分」は、「もう死にます」と死を予告する女からそう聞かされる。
「自分」が「いつ逢いに来るかね」と聞くと、 「日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちて行くうちに、あなた、待っていられますか」
「自分」はうなづくと、女は声を一段と張り上げ「百年待っていて下さい」 と、思い切った調子で言い、さらに「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」と言う。
「自分」はただ待っていると答え、女はそのまま死んでしまう。
自分は約束通り、この美女を葬り、苔の上に坐り、腕組みをして、太陽が登り沈むを何度も見ながら、女の言葉だけを信じて待つ。百年のあいだ。
ところが女は約束どおり現れない。唐紅の天道がのそりと東から上っては、また黙って西 に沈んで行くが何度もある。
「自分」は日の出と日没を、一つ二つと勘定し続ける。
だが勘定しても、勘定しても、赤い日が頭の上を通り越して行くだけで女は現れない。
そしてしまいに「自分」が苔の生えた墓石を眺め、「だまされたか」と思っていた矢先、真っ白な百合が一輪が咲く。
その茎の先に細長い蕾が、ふっくらと開き、まっ白な一輪の百合の花が咲く。
その花は、鼻先で骨にこたえるほどの強い香りを放っている。
そこへ天上から、ぽたりと露が落ちる。花はふらふらと動き、「自分」は首を前へ出す。そして露の滴るその百合の白い花弁に夢中にキスする。
キスした後に遠い空を仰ぐと、暁の星が瞬いているのを眺め、気づくーーー。
「百年はもう来ていたんだな」と。
夢十夜の「第一夜」テーマは?
第一夜は夢幻的な作風で、死んだ女の再来を百年待つ、美しい愛の物語で、<夜>の夢の深い世界を描いた幻想的な作品です。
キーワードとしては、
- 「女」
- 「アニマ」
- 「水鏡」
- 「生と死」
などさまざまな角度から読める作品です。
この作品はいわば、イメージの世界です。つまり、文体すべてで現実感を取り去ることで象徴的なイメージ化を行って、男女の関係を人間臭くない神秘的なまでに美しく、詩的に描いた作品です。
イメージ化を行うことで”超現実的な事態”があらわれて、日常的に常識とされている論理だったり、感覚だったりを無化させて、非現実感を受け入れやすいようにしています。
第一夜の考察と解説【←フカヨミポイントだよ】
「百年はもう来ていたんだな」とはどういうことか?
物語を読んでいると、「百年経っていた」というのは、唐突な感じを受けなくもないですよね。
では主人公はなぜ「百年経っていた」と気づいたのでしょうか?
それは「女=百合の花」であることに思い当たったのです。
「百年、私の墓の傍そばに坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」
つまり自分は「女が女の姿をとって現れるもの」だと思っていたわけです。
ところが女は『百合の花』に転生して目の前に現れたのです。
そのことに気づいたため「ということは、百年はもう来ていたんだな」とふと気づいたわけです。
「百年待っていて下さい」、百年が意味する時間の象徴とは?
死にゆく女が「百年待っていて下さい」の意味は?
まずここでいう「百年」とは、僕たちの世界の時間とは質的に異なっています。百年とは「途方も無い年月」です。
だからその「途方もなさ」をこの百年で表現しているのだと思います。
いわば「超越的」で「象徴的」な時間のことだ、ということを覚えておいてください。
つまり、ここでいう「百年」とは「死」だと言うことです。
「自分」は死に瀕した女の「百年待っていて下さい」という言葉を信じで待ちますが、最終的に美しい女は白百合の姿をとって「自分」の目の間に表れて、再会を果たします。
さてここの「自分が百年待っている」という姿勢は、「死」を受け入れる姿勢です。
そして美女と再会を果たして、「百年はもう来ていたんだな」と気がつくの は、「自分」がそのとき死んでいるということに気づくと言うことです。
さてここで悲劇的なことに気づきます。
それは、美しい女と出会うためには、「死」というものを経ないといけないということ。
「自分」は「百年待っていて下さい」という言葉を信じで待っているのですが、美しい女は白百合の姿をとって、再会します。
これを意味することはなんでしょうか?
それは二人というのは「死」を乗り越えた先にしか会えない、ということを象徴しています。
上記のことは、漱石の願望の現れかもしれません。柄谷行人が言うように。
漱石が生においては禁じられ彼岸(死)においてのみ許容 されるような恋愛体験をもったことは疑いがないが、ぼくがいま重視するのは彼のむしろ成就不能なものへあえてのめりこんでいくと いう傾向性であり、つまり社会的生においてはとうてい充たしえない自己実現を「死」の彼岸に志向する根深い傾向性である。たしかに死は僕の勝利だ(中略)。
つまり、通常の時間制を乗り越えた先にあるのは「死」であり、「死」が成就することでこの世では果たせない自己実現が成就することをあらわしているのです。
なぜ百合の花なのか?
漱石文学では百合の花は、愛の象徴です。
例えば、代助と三千代二人の悲劇の物語「それから」。
雨の中たちのぼる百合の強い香。その匂いに耐え切れなくなる代助。学生時代、まだ三千代の兄が生きていた頃に、代助が三千代と兄に、はじめて百合の花を持参した思い出の花。
つまり百合は二人の愛をつなぐ象徴の花なのです
第一夜においても百合を「愛」というニュアンスで読めば、「愛の話」という角度からも解釈できます。
さらにいえば、「百合」というのは、「百」と「合」と分解できて、百年の会合という含みある言葉とも感じられます。
官能的な百合の花
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て留まった。と思うと、すらりと揺ぐ茎くきの頂きに、心持首を傾かたぶけていた細長い一輪の蕾が、ふっくらとはなびらを開いた。真白な百合が鼻の先で骨に徹こたえるほど匂った。そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴したたる、白い花弁はに接吻せっぷんした。
上の場面は、「女」の生まれ変わりである百合に、「自分」がキスする場面。
非常に女性的に百合の花を描いていて、どこか官能的な感じがします。
さてここで思うのはなぜ「自分」が百合にキスをしたのか?という点。
なぜならまだこの段階では、百合の花が女だとわかっていないからです。あくまで百合の花という認識です。
ぼくが思うのは、おそらく「自分」の言葉にできない「本能的な行動」だったのだと思います。
つまり、頭で考える前にもう行動にしていた、のだと思います。
だから、
ではそれをさせたのはなんなのか。それは「骨に徹こたえるほど匂った」という「匂い」だと思うのです。
その前にある「真っ白な百合」「骨にこたえるほどにおった」という表現も、女を思わせるし、官能的である。愛の成就にふさわしい場面とも言える。
しかし、B案をとりたい。「自分」は、「思わず接吻」したのであり、ここで愛が成就した、女と再会したと明確に意識してはいないからだ。B案の箇所ではじめて「気がついた」とある。また、「百年はもうきていたんだな」といえるのは、「女」が「会いに来ていたのだ」という判断がなければならない。このBの場面で初めて「百合」が「女」と理解したのである。
「暁の星が瞬いている」の「暁の星」とは?
百合とのキスが終わった後このような表現があります。
自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
さてここで「暁の星」はどんな時刻を指すのでしょうか?
それは「暁」とは「夜明け前後」です。つまり夜が開ける前の段階です。
ここでつまり「新しい日が訪れる「再生」のイメージとともに、100年間待ち続けた愛が成就した「実現の明るさ」を表現しているのだと思います。
「黒い瞳」に映る「自分」とは?
女はぱっちりと眼を開あけた。大きな潤のある眼で、長い睫に包まれた中は、ただ一面に真黒であった。その真黒な眸の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。
第一夜では、ある美しい女の臨終を看取っているシーンがあります。彼女は血色の良さそうな顔からとうてい死にそうに見えない。 でも美女は「もう死にます」と静かな声ではっきり言います。「自分」もその言葉に対して疑うわけではなく「確かにこれは死ぬな」と思います。
そして「自分」はその美しい女の見開いた目を覗き込みます。
「大きな潤のある眼で、 長い睫に包まれた中は、只一面に真黒」で、その真っ黒な瞳の奥にはなんと「自分」の姿が鮮やかに浮かんでいます。
「自分」は彼女に言います。「私の顔が見えるかい?」と。すると美女はこのように言います。「見えるかいって、そらそこに写ってい じゃありませんか」。
ここって非常に、不思議ですよね。
なぜなら「そこに」という表現。いま美しい女は「自分」に見られているはずなのに。
「そこに」というのはまるで、他人事のような、あるいは外にいるような口ぶりです。
ここの意味なのですが、実はこの女は「自分」の「内部にいる存在」と読めます。
つまり、彼女の存在がまるで目の前にいるかのように読めるのは、「自分」の内にいる「存在」を外に投射しているんです。その姿が死に瀕しているということは、それは「自分自身の臨終の姿」であるわけで、自分の瞳に映る影像としてはっきり見ているのです。
ではこの「内部にいる存在」とは、死んで埋没しようとして いる、「自分」=理想の女性像=アニマだとも読めます。(この点は次の章で説明します)
また「鏡」と言う関係で読み解くこともできます。「第一夜」では下記のように二重構造をなしています。
- 女の瞳に映っている「自分」
- それを見守っている実在の「自分」
ここでは女の瞳=鏡に映っている自己と、それを映す女との関係は、まるで鏡の跳ね返りのように、「自分」への自己認識が跳ね返って、女の「自分」に対する認識でもあるという密着で不可分な間柄でもあります。
つまりここに描かれているのは、二人の関係の結合的かつ集約的なイメージでもあります。そもそもどれだけ愛する男女であっても、他者である以上、完全なる結合は難しいですよね。でも「瞳という鏡」を介してなら、「自分」は女の瞳という内なる映像に映り、それを見守る「自分」とが二重構造になり、生身の肉体ではないけれど、「関係」という意味では結合的な要素もあるのです。
「アニマ」との関係性で読む
アニマは精神科学者のユングが提唱した概念で、「男性の集合的無意識に存在している女性像」です。つまり第一夜の物語は、「自分」(=漱石)の深層にいる「アニマ」との再会の物語でもあります。
しかしながら物語は悲しいですよね。なぜならお墓の前で百年忠実に待っても、生身の肉体を持った女性とは再開できないのですから。姿は「百合の花」をとっています。
つまりこれが象徴しているのは、自分自身の生命力の根源となる「アニマ」とは、この世だけでなく、死を乗り越えたとしても、完全な関係を結ぶことができないことなのです。
最初死に瀕している女性とは、生命力の無くなった己自身のアニマであって、己の手でアニマを葬って再会を夢見ったのですが、蘇生したとしても、理想の女性である=アニマは手が届かないのです。