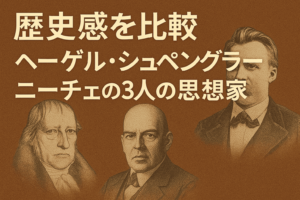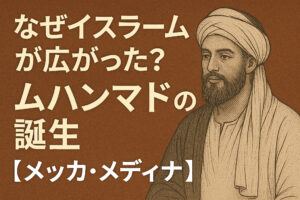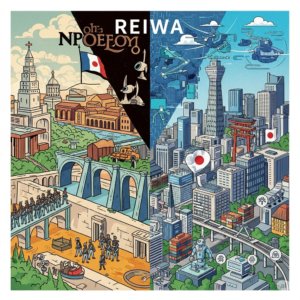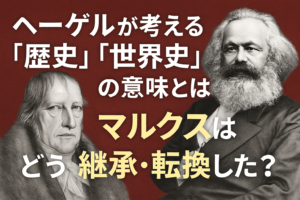「歴史って、結局いつ・誰が・何をしたかを覚える学問でしょ?」――もしそう思っているなら、E.H.カーの『歴史とは何か』はあなたの常識を真っ向から揺さぶる一冊です。
カーは、「歴史とは単なる事実の集積ではなく、未来を方向づける知的営みだ」と喝破しました。
本記事では “初めてカーを手に取る読者” に向けて、エッセンスをギュッと凝縮。読後には「じゃあ自分の毎日やビジネスにどう活かせる?」というところまで解説しています。――そんな実践的イメージをお約束します。
歴史とは何か?
歴史とは、過去と現在との対話である
歴史というのは現在の眼を通して、現在の問題に照らして過去を見るところに成り立つものであり、 歴史家の主たる仕事は記録することではなく、評価することである
歴史とは、過去に起きた出来事そのものではありません。現代を生きる私たちの問いに応える形で史料を選び取り、意味づけ直した「再構成された過去」――これが E・H・カーの核心的な主張です。
「歴史」という言葉にはふたつの意味があります。1つは過去に実際に起こった出来事、もう1つはそれを研究・記述する営み。カーやコリングウッド、オークショットが重視したのは後者。
「過去の出来事がそのまま歴史になるのではなく、歴史家がその出来事に意味を与えて“再構成”することで初めて歴史になる」
という考え方です。
私たちはつい「○○年に△△城が築かれた」といった年号や出来事の羅列を“歴史”と思いがちです。つまり「歴史とは過去の出来事を記録すること」と考えがちです。しかし、カーはそれでは不十分だと考えます。
しかし歴史とは、単に「何が起こったか」を書き残す作業=記録ではなく、むしろ大切なのは、「その出来事にどんな意味があるのか?」を現在の目で問い直すことです。
カーが「歴史家の主たる仕事は記録することではなく、評価することである。」といっているように、現在の問題意識や未来へと結ぶ動的プロセスにほかならず、歴史とは、現在の目で過去を見直し、そこに意味を与える知的な営みであるということです。
 たかりょー
たかりょー記録するだけでなく、評価し、問いを立て、未来へつなぐ――それが歴史家の本当の仕事なのです。
したがって歴史家は単なる「事実の記録係」ではなく、史料の「選択」と「解釈」を通じて過去をモデル化する思考者です。彼らは膨大な資料の中から「いま私たちにとって意味を持つ断片」を選び出し、因果関係や文脈を組み立てることで“歴史像”を提示します。
なぜ「現在の目」が必要なのか?
カーにとって、歴史は現在と切り離せないものです。なぜなら、僕たちが「なぜこの過去に注目するのか」と問うとき、そこには私たちが抱える今の課題や関心が必ず影響しています。
たとえば
- ある国の戦争を詳しく学ぶのは、「同じ過ちを繰り返したくない」から。
- 過去の疫病や危機を調べるのは、「今のパンデミックにどう向き合うか」を考えるため。
このような目によって歴史は解釈されていくわけです。
「歴史的事実」は選ばれた物語である=恣意的
一〇六六年にヘスティング スで戦闘が行なわれたことを知りたいと私たちが思う理由は、「ただ一つ、歴史家たちがそれ を大きな歴史的事件と見ているからにほかなりません。シーザーがルビコンという小さな河 を渡ったのが歴史上の事実であるというのは、歴史家が勝手に決定したことであって、これ に反して、その以前にも以後にも何百万という人間がルビコンを渡ったのは一向に誰の関心 も響かないのです。みなさんが徒歩か自転車か自動車で三十分前にこの建物にお着きになっ たという事実も、過去に関する事実という点では、シーザーがルビコン河を渡ったという事 実と全く同じことであります。
P9
現代のジャーナリストなら誰でも知っているように、世論を動かすには「どんな事実を選び、どう並べるか」がカギになります。同じように、歴史家もまた「事実の並べ方」によって過去を語ります。
よく「事実は自らを語る」と言われますが、E.H.カーはこれをきっぱり否定します。
事実は、歴史家が「語ってほしい」と呼びかけたときにだけ語るのです。
つまり、歴史家がどの事実に目を向け、どんな順番で、どんな意味を持たせて語るかによって、歴史は形づくられるということです。つまり
いつも記録者の心をつうじて屈折して来るもの
P25
たとえば──シーザーがルビコン川を渡ったことは有名な「歴史的事実」として知られています。でも、同じ川を渡った何百万という無名の人々の行為は、歴史には残っていません。
なぜか?それは、歴史家がその出来事を「意味あるもの」と判断するかどうかで決まるからです。
エンゲルスの「アイルランド史」から見る歴史
エンゲルスが『アイルランド史』という書物の中で、アイルランドがイギリスによって「歴史的に同化されるべき運命にある」とする言説が、いかにして歴史家たちの「事実」の選び方によって構成されたかを批判的に描いています。
たとえば、イギリスの地学者は、アイルランドには農耕に向かない土壌が広がり、石炭も採れないという「事実」を提示します。一見すると自然科学的な中立の情報に見えるかもしれませんが、それは「アイルランドは産業化できない」「したがって、永遠に牧草地としてイギリスに従属すべきである」という解釈を正当化するために使われているのです。
このように、いかに「事実」が中立のように見えても、それは常に選ばれ、配列され、文脈づけられた「解釈の一部」であるという点において、カーの主張と重なります。カーも『歴史とは何か』で、「事実はみずから語るのではなく、歴史家に呼びかけられて初めて語る」と述べました。つまり、どの事実を選ぶか、どう並べるか、どのような文脈で提示するかによって、事実はまったく異なる意味を帯びるのです。
アイルランドの地理や資源に関する分析が、アイルランドの独立や工業化の不可能性を証明する道具にされていたとすれば、それは単なる自然の記述ではなく、政治的目的に奉仕する歴史的語りであったということになります。
このような歴史叙述の構造は、カーが繰り返し強調した「事実と解釈の不可分性」を示す生きた事例といえるでしょう。エンゲルスが見抜いたのは、歴史家の語る「事実」が、常にある視点や価値観から選ばれたものであるということ、そしてその選び方自体が歴史の方向性を左右してしまうという根本的な問題だったのです。
すべての歴史は思想の歴史である
ここでいう「思想」とは、単に政治思想や哲学ではなく、歴史家が過去に向ける問い・視点・価値判断を含んだ広い意味での“考える力”です。
- どの事実を取り上げるか
- どの順序で語るか
- どのように意味づけるか
これらはすべて、歴史家の頭の中で行われる“再構成”のプロセスです。したがって、カーはこう言います。
「過去は、歴史家の心の中で再構成されたときにはじめて意味を持つ」
「歴史とは、なお現在に生きている過去のことである」
カーが考える「社会と個人」の関係とは?
ある時代の偉人というのは、彼の時代の意志を表現し、時代の意志をその時代に向って告げ、これを実行することの出来る人間である。彼の行為は彼の時代の精髄であり本質である。彼はその時代を実現するものである。
偉大な著述家は、「彼が人間の自覚を進めるという点で重要なのである」とリーヴィス博士は言っていますが、これも同じ意味であります。いつも偉人というもの は、現存の諸力の代表者であるか、さもなければ、彼自身が現存の権威に挑戦してその創造 を助けようとしている諸力の代表者であります。しかし、ナポレオンやビスマルクのように、 既存の諸力に跨って偉大になった人々に比べますと、クロムウェルやレーニンのように、自分たちを偉大にさせた諸力そのものを作り上げるのを助けた偉人の方に、一層高い創造性が 認められるのではないでしょうか。また、自分の時代より進み過ぎていたために、ようやく 後代に至ってその偉大さが知られるようになった偉人たちのことも忘れてはなりません。私が大切だと考えますのは偉人とは、歴史的過程の産物であると同時に生産者であるところの、また、世界の姿と人間の思想とを変える社会的諸力の代表者であると同時に創造者であ
るところの卓越した個人であると認めることであります。」
それゆえに歴史というのは、この言葉の二つの意味で―――すなわち、歴史家が行なう研
究という意味でも、歴史家が研究する過去の事実という意味でも――一つの社会過程であり まして、個人は社会的存在としてこの過程に入り込んでいるのであります。社会と個人との
「歴史とは、ある時代が他の時代のうちで注目に値いすると考えたものの記録」であります。
P77〜78
過去は、現在の光に照らして初めて私たち に理解出来るものでありますし、過去の光に照らして初めて私たちは現在をよく理解することが出来るものであります。人間に過去の社会を理解させ、現在の社会に対する人間の支配 力を増大させるのは、こうした歴史の二重機能にほかなりません。
E.H.カーにとって、歴史における「社会と個人」の関係とは、どちらか一方に重きを置くものではなく、相互に作用し合う動的なプロセスとして捉えるべきものでした。
個人は社会の中で生き、その行動や思想は必ず時代や社会の背景に影響を受けています。たとえばナポレオンやビスマルクのような人物は、すでに存在していた政治的・社会的な力を利用してその名を残した点で、時代の流れの中にいた人物といえます。つまり、彼らは「時代の産物」として理解されるべき存在です。
しかし同時に、歴史のなかには、まだ明確に形になっていない新しい価値や社会の変化の兆しを察知し、それを言葉や行動として先取りする人間もいます。たとえばクロムウェルやレーニンのように、自らが時代を動かし、歴史の方向性そのものを変えた人物たちです。こうした人物たちは、単に時代に乗ったのではなく、時代そのものを創造する力を持っていたと言えるでしょう。
カーはこうした両面性を踏まえ、
「偉人とは、歴史的過程の産物であると同時に、その生産者でもある」
と述べました。つまり、偉大な個人というのは、社会の中で生まれ育まれた存在であると同時に、社会に影響を与え、変化をもたらす存在でもあるということです。
このようにして歴史は、社会の力が個人を形づくり、個人の行動が社会を変えていくという、双方向の働きの中で動いていきます。
歴史とは、個人の物語でもなければ、社会構造の単なる記録でもなく、その両者のあいだにある緊張や交差の中から浮かび上がる、複雑で生きたプロセスなのです。



「歴史家も研究対象も、ともに社会の産物」 という視点。すなわち歴史記述とは “私=現代社会” と “彼ら=過去の社会” の対話であり、価値観・時代背景から完全に自由な記述は不可能だと説く。
カーの歴史観は、英雄的な個人の力を過大評価することも、社会的構造の圧倒的な力だけに注目することもありません。むしろそのどちらも必要不可欠であり、歴史とはそのあいだにある「対話」や「関係性」の中から読み解かれるべきものであると考えました。
歴史的事実は「個人の行為」だけでは語れない
歴史上の事実は、諸個人に関する事実に相違ありませ んけれども、孤立した個人の行為に関する事実でもなければ、諸個人がみずから行為の動機 「―と称するもの――真実のものであれ、架空のものであれ――に関する事実でもありません。 それは社会のうちにおける諸個人の相互作用に関する事実であり、また、諸個人の行為から、 こしばしば彼らみずからが意図していた結果とは食い違った、時には反対の結果さえ生み出す ような社会的諸力に関する事実なのです。 前回の講演で申し述べましたコリングウッド史観の最も重大な誤謬の一つは、行為の背後 にある思想――これを究めるのが歴史家の使命なのですが 「したところにあるのです。これは誤った仮定であります。歴史家が研究を託されているのは、 ―を行為する個人の思想と仮定 「行為の背後に潜んでいるものですが、それと、 と『行為する個人の意識的な思想や動機とは全く 関係がないかも知れないのです。
「歴史上の事実」は確かに個人に関する出来事である、と認めます。でも、そのうえで、
「それは孤立した個人の行為ではなく、社会の中での人と人との相互作用に関する事実である」
つまり──
- 「Aさんが何をしたか」だけを見ても歴史はわからない
- その行動が「どんな社会的文脈の中で」「どんな他者との関係で」行われたか
- そして「その結果が社会にどんな影響を及ぼしたか」まで考えなければならない
たとえ本人の意図がAでも、結果としてBやCが起こることが歴史には多々あります。
コリングウッドという歴史家は、歴史家の使命は、行為の背後にある“思想”を理解することだ。といってますが、カーは「その“思想”が、行為した本人の意識的な動機や意図と一致するとは限らない」と批判します。
つまり、歴史家は「人物の内面の再現」にばかり集中すべきではなく、むしろ、その人物の行為が社会にどんな「意図せざる結果」をもたらしたかまで追うべきだと考えています。



歴史は「個人の内面」より「社会の力学」を見るものです。つまり、「ひとりの人間」の内面を丁寧に追えばわかるものではなく、行為が生み出した「社会的な動き」や「相互作用」を重視しなければなりません。
だからこそ、歴史とは「構造」と「関係性」と「文脈」を理解する知的営みと考えていいですね。
事実と価値は切り離せない
「価値とは普遍的でも絶対的でもなく、歴史的に形成されたものだ」
カーは、「平等」「自由」「正義」「自然法」など、いかにも普遍的・絶対的に見える価値ですら、
実際には「その時代とその社会が生み出した歴史的産物」だと言います。



たとえば、「自由」という言葉一つとっても──
・18世紀のフランス革命の「自由」
・19世紀アメリカの「自由」
・20世紀ソ連の「自由」
……それぞれ意味も中身も違うのです。
人間の集団(国家・民族・文化)は、自分たちが信じてきた価値観を「当然のもの」として守ろうとします。だから、異なる価値観に対しては「ブルジョア的」「全体主義的」「非〇〇的」などとレッテルを貼って排除しがちです。でも、それは価値に「超歴史的な客観性」を求める姿勢であり、カーにとっては幻想にすぎない。
「社会から切り離され、歴史から切り離された抽象的な規準や価値というのは、抽象的な個人と同様、幻想である。」
つまり、どんな価値観も「歴史に根ざして」生まれたものであり、それはその時代・その社会の人間たちが環境や経験のなかで築いたものだということです。
では歴史家はどのような姿勢で
カーが求める歴史家とは──「自分たちの価値観ですら歴史の一部である」と認められる人のこと。そして、そうした視点を持つ歴史家は、価値を「批判的に問い直す」ことができます。
| 観点 | カーの主張 |
|---|---|
| 価値の正体 | すべての価値は、時代・社会・文化の歴史的文脈の中で生まれた |
| 普遍的価値? | 存在しない。むしろそれを信じること自体が「歴史を忘れた態度」 |
| 歴史家の役割 | 自分の価値観をも相対化し、歴史的に理解しようとする姿勢が大切 |
| 社会科学との違い | 歴史は「外部から与えられた普遍法則」に頼らず、内在的に価値と出来事の相互関係を読み解く |
「特殊的」と「一般的」は切り離せない
歴史とは、たとえば「ある戦争」「ある革命」「ある偉人」といった一回きりの具体的な出来事(=特殊的なもの)を扱う学問です。
しかし、その出来事を「なぜ起こったのか」「他とどう違うのか」と考えるとき、その背景や共通性(=一般的なもの)を探らずにはいられません。
- たとえばフランス革命を研究する場合、フランスという国の特殊事情を調べるだけでなく、「なぜこの時代に革命が多発したのか」「他国の革命とどう異なるか」といった普遍的な構造を考察する必要があるのです。
カーは、歴史において「事実」と「解釈」が切り離せないと繰り返し述べています。それと同じように、個別と一般(特殊と普遍)も切り離せないのです。
- 個別的な出来事は、一般的な理解なしに意味づけできない。一方、一般化とは常に個別の事例からしか導かれない。
だから、どちらが上でどちらが下という関係ではなく、歴史家はこの両者のあいだを絶えず行き来することが求められるのです。
過去と未来をつなぐ──「どこへ向かうのか」を問う



カーは「なぜ起きたのか(Why)」だけでなく、「どこへ向かうのか(Where to)」も歴史の核心だと言います。
E.H.カーは、歴史とはただ「なぜそれが起きたのか(Why)」を問い続けるだけでなく、「どこへ向かっているのか(Where to)」を考える営みだと強調しています。
これは、過去を理解することがそのまま未来への洞察や方向づけにつながるという考え方です。
たとえば「人類はこれからどこへ向かうのか?」あるいは「明治維新の延長線上にある現代日本はどうあるべきか?」といった問いは、歴史を現在の羅針盤として活用する視点を促します。
単なる出来事の記録にとどまらず、そこから導き出される教訓や知見をどう未来に生かすかが問われているのです。
そして最後に、こんな問いを自分自身に投げかけてみることも勧められます
――いま関心のある社会問題について、「未来の歴史家はどう評価するだろう?」と想像してみる。そうすることで、私たちが今取るべきアクションや選択の意味が、よりクリアに見えてくるかもしれません。
歴史は、私たちが未来を考えるための一つの知的な「装置」なのです。
- 未来志向の問い
・人類はこれからどこへ向かうのか?
・明治維新の延長線上に、現代日本はどうあるべきか? - 歴史を羅針盤に
単に出来事を追うのではなく、学んだ教訓をどう未来に活かすかを考えましょう。



いま関心のある社会問題を、「未来の歴史家はどう評価するだろう?」と想像してみると、今やるべきアクションが見えてくるかもしれません。
科学と歴史の共通点がある?
歴史学と科学には共通点もあれば、大きな違いもあるんです。
まず、共通点として注目したいのは、「因果性を探ろうとする姿勢」です。たとえば、歴史学も「特定の条件下で、特定の結果が起きやすい」という蓋然性(確率的な因果関係)を重視します。
たとえば――
- なぜ革命が起きたのか?
- どんな社会条件のもとで感染症が広がったのか?
こういった問いに対し、歴史学は社会科学や自然科学と同じように、「再発するかもしれないパターン」を探ろうとするんです。
でも、だからといって「歴史=科学」とは言い切れません。
最大の違いは、「変数の多さと複雑さ」です。
科学では、「他の条件が変わらないとき(ceteris paribus)」という前提で、1つの要因の影響を測るのが基本。でも、歴史ではそうはいきません。
出来事の背後には、
- 政治や経済の構造、
- 個人の意思や感情、
- 文化や宗教、技術革新や気候変動…
といった無数の要因が同時に絡み合っているため、「すべての条件を固定した上で比較する」なんてことは現実的に不可能なんです。
だから、歴史学には「厳密な実証主義」だけでは説明しきれない部分があります。
それでも、カーは歴史学が他の学問と対話することを大切にしていました。カール・ポパーの反証可能性や、トクヴィルの比較歴史、構造主義やフランクフルト学派など――科学や社会学の理論を取り入れつつ、語り物としての歴史の個性も忘れないようにと言っています。
こうした視点は、「すべての出来事には原因があるのか?」という問いにもつながります。
カーは、決定論(determinism)についてこう述べています。
「決定論とは、すべての出来事には一つあるいは幾つかの原因があって、その原因に変化がない限り、出来事に変化は起こらない、という信仰である」
この言葉が示すように、歴史を学ぶ上で「なぜ?」を問う態度は避けて通れません。ただし、あくまで確率的・相互作用的に、柔軟に因果を捉えることが、歴史学においては重要なのです。
歴史理解を深めるために、僕らができること
歴史を学ぶときに意識したい2つの視点
歴史をただ「覚えるもの」として捉えると、過去の出来事の羅列に見えてしまいがち。でも、E.H.カーのような歴史家の視点に立てば、「どんな事実をどう見るか」で歴史の意味がガラッと変わってくるんです。
そこでポイントになるのが、次の2つの問いです。
① その事実、他でも通用する?(一般化できるか)
歴史を学ぶ目的のひとつは、過去から教訓を得ることです。そのためには、ただの一回限りのエピソードではなく、他の時代や場所にも当てはまりそうなパターンや傾向に注目したほうが有意義です。
たとえば…江戸時代の飢饉で起きた一揆→ 単なる暴動として見るのではなく、「権力と民衆の関係」「経済的不満が社会運動を生む」など、現代にも通じる要素に目を向ける。
② それって、何を知るための事実?(目的に合っているか)
歴史の“意味ある事実”は、「自分が何を知りたいのか」によって決まります。すべての事実が等しく重要なわけではなく、「問い」によって光の当て方が変わるんです。
たとえば…「明治維新はなぜ起きたのか?」を考えたいなら、
→ 西郷隆盛の人柄よりも、農民の負担や列強の圧力など構造的な要因に注目したほうが本質に近づけます。
歴史を学ぶのは、じつは「いまの自分」と「過去」との対話です。だからこそ、
- 自分は何を知りたいのか?
- そこから何を学び、どう未来に活かせるのか?
という視点を持つことで、歴史の見え方がどんどん変わっていきます。
2. 自分なりの「問い」を立ててみよう
歴史家も「なぜ」と尋ね続 けるところの動物なのです。
歴史家は、出来事をただ記録するのではなく、「なぜ」を問い続けます。
つまり、歴史家とはこういう問いを立て続ける人のこと:
- 「なぜ、それが起きたのか?」
- 「どんな力が背景にあったのか?」
- 「そこから私たちは何を学べるのか?」
事実をただ集めるのではなく、意味と関連性を見出すことこそが、歴史家の仕事なのです。
これは僕たちの日常にも応用できそうです。「“なぜ”」という問いは3つの大きな意味があります。
| 観点 | なぜ「なぜ」が重要なのか |
|---|---|
| ① 原因を解明する | 出来事の裏にある構造や背景を明らかにするため |
| ② 解釈の幅を広げる | さまざまな立場や視点から歴史を読み直せる |
| ③ 未来へのヒントになる | 「なぜ」を掘り下げることで、今とこれからの道しるべが得られる |
たとえば、フランス革命について学ぶとき――
ただ「1789年に起きた」と覚えるだけでは何も残りません。
でも「なぜ起きたのか?」と考えると、
- 経済の格差?
- 政治の閉塞?
- 新しい思想の広がり?
というふうに、今の社会にも通じる視点が見えてきますよね。
カーは人間とは「なぜ」と問う存在であるとも言っています。
つまり、歴史家だけでなく、私たち一人ひとりが「なぜ」と問い続ける力を持っている。
それは、自分の人生、社会のあり方、そして世界全体を見直すための、とても人間らしい営みなのです。
書くことで問いが深まり、意味が見えてくる
私自身について申しますと、自分が主要史料と考えるものを少し読み始めた途端、猛烈に腕がムズムズして来て、自分で書き始めてしま うのです。これは書き始めには限りません。どこかでそうなるのです。いや、どこでもそうなってしまうのです。それからは、読むことと書くこととが同時に進みます。読み進むにしたがって、書き加えたり、削ったり、書き改めたり、除いたりというわけです。また、読む ことは、書くことによって導かれ、方向を与えられ、豊かにされます。書けば書くほど、私は自分が求めているものを一層よく知るようになり、自分が見出したものの意味や重要性を一層よく理解するようになります。
この文章から読み取れることは、「読む → 書く → さらに読む → また書く」という循環が、歴史家の思考を育てていくのです。
つまり
- 資料を読んでから書くのではなく、書くことで何を読むべきかが見えてくる。
また
書けば書くほど、自分が何を求めているのかがよくわかる。
書くことで、見出したことの意味や重要性も明確になる。
といっているように書くという行為そのものが、問いを深め、理解を深めて歴史を書くことは、過去と現在をつなぐ「創造的な営み」**である。
「歴史を書く」ということが、知的な労働であると同時に、身体的な実感を伴う創作行為だということです。
彼はただ知識を整理して記述しているのではありません。
書くことで「自分の考え」そのものを形にし、育てていく。
このダイナミックなプロセスこそが、カーの歴史観そのものに通じています。
まとめ
E.H.カーにとって、歴史とはただ「過去に何が起きたか」を記録することではありません。
むしろそれは、人間が価値をもとに世界を読み解き直し、未来に向けて意味をつくり出していくプロセスだとされます。
歴史家の役割は、事実と価値の間に立ち、その関係を問い続け、結び直し続けること。
そしてこの姿勢は、歴史を学ぶすべての人にも求められる「知的な責任」だとカーは語ります。
カーが言う「歴史的真理」とは、ただ一つの“正解”ではなく、変わり続ける現実の中で、私たちがどこに意味を見出し、どう未来を切り拓いていくかを問う、“生きた知”のことなのです。