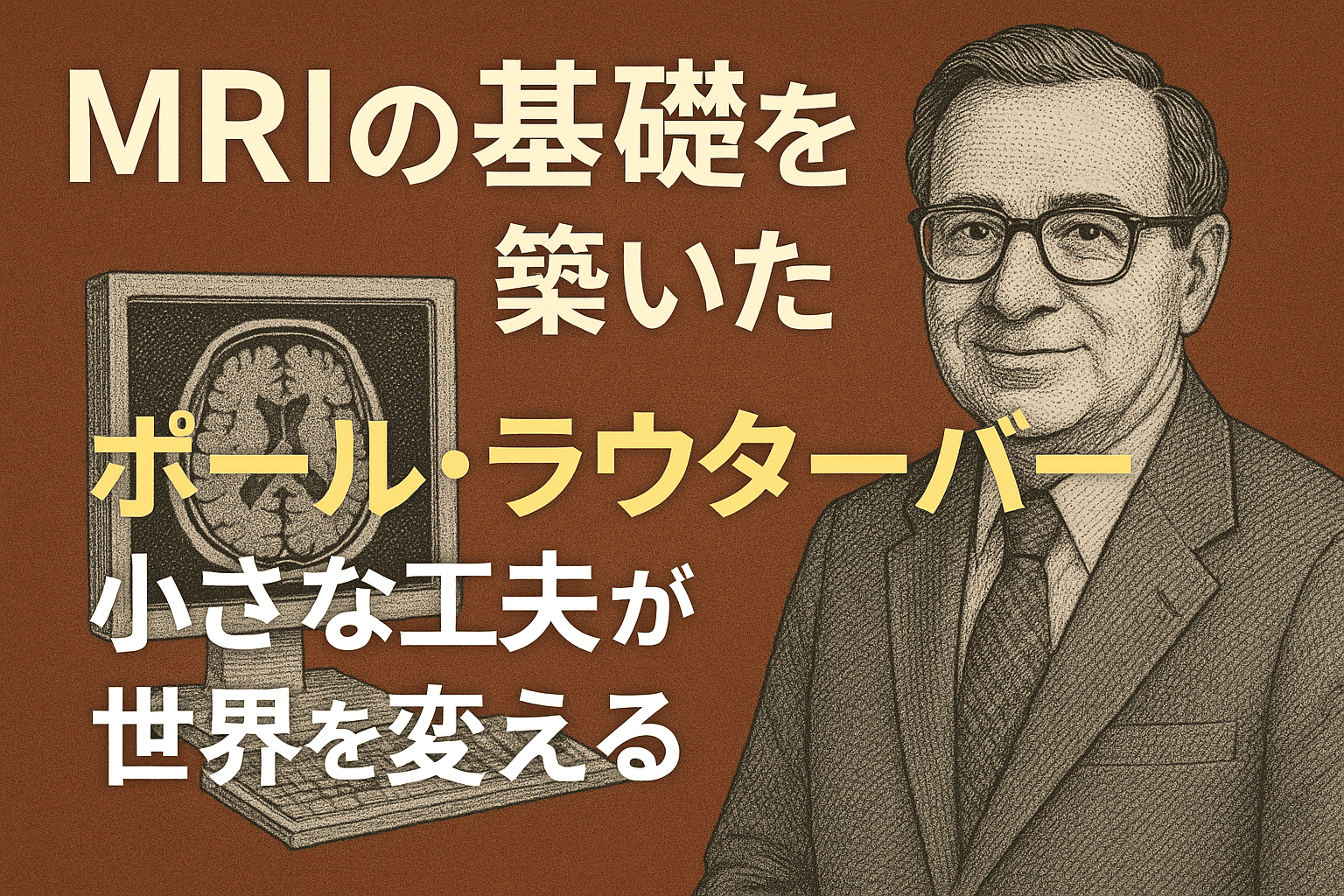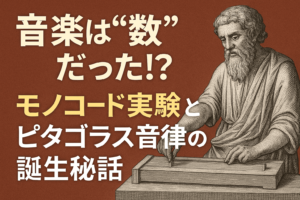たかりょー
たかりょー今回紹介する偉人はポール・ラウターバー博士。
彼の偉業はMRIという「体の中をのぞく」技術の基礎を作ったことです。
MRIは今や、がんの早期発見、脳の病気、内臓の検査などに欠かせない技術。それが可能になったのは「磁場をちょっとだけ傾けてみたら…?」と考えた、ほんの小さな工夫。
この工夫こそが、それ以後、世界中の大勢の人々を支える技術になったのです!
ポール・ラウターバーとは?
ポール・ラウターバー(Paul Lauterbur)博士はアメリカの化学者。現代の医療に不可欠な「体の中を見える化する技術」であるMRI(磁気共鳴画像法)の基礎を築いた人物。
当時ラウターバー博士は、役員を務めていた企業が経営危機に直面していたことをきっかけに、核磁気共鳴原理 (NMR)を医学に応用できないかと考えました。そこで目をつけたのが、自身が長年研究していた核磁気共鳴(NMR)という技術です。



背景:NMRの限界
MRIが発明される前、物質の内部構造を調べるために使われていたのが、核磁気共鳴(NMR:Nuclear Magnetic Resonanceという技術です。
■ NMRってなに?
原子の中心には原子核があり、これには「スピン(自転のような性質)」があります。
このスピンは、小さな磁石のような性質を持ち、ふだんはバラバラな方向を向いています。
しかし、磁場の中に入れると……スピンが整列!さらに高周波の磁場(ラジオ波)を加えると、特定の周波数で「共鳴」が起きて、NMR信号が発生!
このNMR信号を測定することで、分子の構造や性質がわかるというわけです。
■ でも、医療に使うには問題が…
NMRはとても優れた分析技術ですが、ひとつ大きな問題がありました。
それは――「信号が、試料のどこから来たのか」がわからないということ。
つまり、
- 「この信号は“どの場所”のものか」
- 「体の“どこに”異常があるのか」
といった空間的な位置情報がまったく得られなかったのです。
だからこそ、当時は――
- 組織を体から取り出して小さく切り、試験管に入れてNMR測定する
- 結局、体を切開して調べるしかない
という状況だったのです。
例えていうなら、NMRはにおいを嗅いで「カレーがある」とわかるけど、どこにあるかはわからないみたいなことです。



たしかにカレーの香りはする。でも、それが部屋のどこにあるか、何皿あるか、どんな器に入っているかは見えない状態。
つまり、“中身の正体”はわかっても、“位置や形”はつかめないのがNMRの限界でした。
ラウターバーのひらめき:傾斜磁場
化学者だったラウターバーは、こう考えました。



「NMRに位置情報が付けられたら、体を切らなくても中が見えるはずだ!」
ポール・ラウターバー博士は、均一な磁場の代わりに、強さにわずかな傾斜がある磁場(=傾斜磁場)を使うことで、原子核の位置によって異なる周波数の信号が出ることを発見しました。
そこで使ったのが「水分子」。水分子に含まれる水素のNMR信号は、磁場の強さが変わるとその周波数も変わるという性質があります。ちなみに水素原子核はNMRで最もよく使われる対象で、磁場の強さに比例して共鳴周波数が変わる(ラーモア周波数)という性質があります。
つまり──
水素のNMR信号の“周波数=位置”と見なせば、体の中のどの位置に水があるかがわかる!
この発想によって、「どの位置から出た信号か」を特定できるようになり、体内の“水”の分布を画像として再構成することが可能になったのです。
これがMRI(磁気共鳴画像法)の原理の誕生でした。
- 生体内の水素原子核に磁場を当てる
→ 人の体の60%は水。その中にある水素原子核(プロトン)は磁石のような性質を持っています。 - 傾斜磁場を使って、場所によって周波数が変わるようにする
→磁場に傾きをつけると、「体の位置ごとに違う周波数の信号」が返ってくるようになります。
つまり、“音の高さ”で場所がわかるようになるのです! - 集まった周波数データを元に、水の分布を画像として再構成
→体のどこに水がどれくらいあるか=臓器や組織の様子がわかる!
人体の中の“断層画像”=MRI画像が完成!
MRIはそこに、「場所を知るしくみ=傾斜磁場」という発明を加えて、“どこに何があるか”を画像として見せられるようにしたのです。
エッセンス:小さな工夫が世界を変える
ラウターバー博士が行ったのは、「磁場にほんの少しの傾斜を加える」というシンプルな工夫。つまり、ラウターバー博士の発明は、特別な装置や複雑な理論ではなく、磁場にちょっとだけ傾きをつけただけ。
たったそれだけ!でも、それが世界中の病院にあるMRIへとつながり、毎日何千万人もの命を救う技術になったのです。



ここから学べるのは、発見とは、新しいなにかを見つけることだけではなく、同じ景色を新しい目で見る、なのでは?ということです!