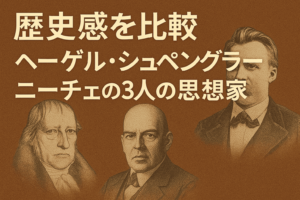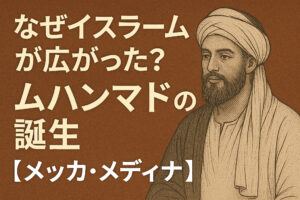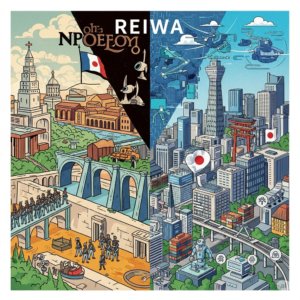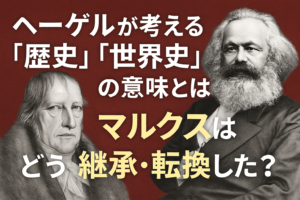「アイルランド問題」という言葉を聞いたとき、単なる反英運動や宗教対立のように受け取られることがあります。
しかし、私がこの問題を深く学んでいくうちに見えてきたのは、それが宗教、民族、階級、土地所有、帝国主義といった複雑に絡み合った問題の結節点だということでした。
この記事では、19世紀から20世紀にかけてのアイルランド史を軸に、「アイルランド問題とは何だったのか?」を考えてみたいと思います。
アイルランド問題とは?
アイルランド問題とは、イギリスによるアイルランド支配と、それに対するアイルランド人の抵抗・独立運動をめぐる歴史的・政治的・社会的な問題を指します。17世紀から20世紀にかけて続いた、民族・宗教・階級・植民地主義が複雑に絡み合った長期的な対立構造です。
アイルランド併合の背景(1801年)──表向きの統合、実態は支配
1801年、イギリスとアイルランドは「連合法」によって合邦し、アイルランドは正式に「グレートブリテンおよびアイルランド連合王国」の一部となりました。
しかし、その実態はアイルランド側の自治の剥奪であり、政治的従属の始まりでした。
アイルランド議会は廃止され、ロンドンの議会に吸収。実権はすべてイギリスに握られることになります。
この背景には、ナポレオン戦争下でアイルランドがフランスと結託することへのイギリスの強い警戒がありました。
宗教と民族の分断:カトリック vs プロテスタント
アイルランド住民の大半はカトリックであり、イギリス支配層(プロテスタント)との間に根深い差別がありました。
特に北部アルスター地方にはプロテスタント系の移民が多く、イギリスとの結びつきが強く、以後の分断の焦点となる。
飢饉と移民──構造的な「民族排除」
アイルランドの「飢饉」「移民」「土地収奪」は、その反動としての「下層階級による民族解放運動」が成立します。
その象徴が、1845〜1849年、アイルランドで起こったジャガイモ飢饉。当時のアイルランド人口の大多数が主食としていたのがジャガイモ。このとき約100万人が死亡し、200万人が国外(多くがアメリカへ)に移民しました。
しかし、飢饉自体よりも問題なのは、その被害の構造的背景です。
イギリスからは下記のような構造的な剥奪がなされていました。
- 飢饉中にもかかわらず、アイルランドからの穀物や牛肉の輸出は継続された。
- アイルランドの土地の多くはイギリス系の地主に所有されており、地代は高騰。
- 家を追われた農民たちは、移民か餓死かの選択を迫られた。
- 飢え死ぬか、移民するしか選択肢はなかった。
僕には、こうした事態が意図的な「民族の清掃(クレンジング)」とも呼べるものに見えてなりません。
移民によって空いた土地はイギリス人によって「再編」され、アイルランドの共同体は崩壊していったのです。
海外移民による民族運動──フェニアンたちの反乱
興味深いのは、アイルランド国内では抑圧が強く直接的な反乱が難しかった一方で、アメリカに渡った移民たちが自由な環境で民族運動の火をともしたという点です。
これがいわゆるフェニアン運動です。「フェニアン」は古代アイルランドの戦士団にちなんだ名前。アメリカのアイルランド系移民が、祖国の解放を掲げて組織化し、イギリス本土での独立運動のための武装行動や蜂起も起こしました。
この運動の主体は、労働者階級や下層民が中心でした。だからこそ彼らの怒りや行動には、単なる民族主義ではない、社会的な怒りの要素も強く感じます。
運動の意義=「下層階級からの社会主義的解放運動」
- 民族の抑圧の廃絶は、階級抑圧の解消への一歩である。
- アイルランドの独立なしに、イギリス本国の労働者階級も団結できない。
- よって、アイルランド問題は「労働者の国際連帯」の試金石である。
合邦によって封じ込められたアイルランドの未来
アイルランドでもフランス革命やアメリカ独立の影響を受けて、共和制や独立の気運が高まっていました。しかしその動きを封じたのが1800年の合邦だったわけです。
 たかりょー
たかりょーこのことから僕が感じるのは、「アイルランドには別の近代化の可能性があったのに、それがイギリスの意図によって閉ざされた」という悔しさです。
- アイルランドの産業は意図的に抑え込まれ、工業化の道は断たれる。
- かわりに農業的後背地として再編成された。
この構造は、現代の言葉でいえば「周辺化」、つまり中心国(イギリス)と周辺国(アイルランド)という支配と従属の関係に重なってきます。
アイルランド問題とは何だったのか?
アイルランド問題は、カトリックとプロテスタントの対立や、土地所有をめぐる農民と地主の軋轢、あるいは飢饉と貧困といった表面的な「国内問題」にとどまりません。
それは資本主義の本質を暴露する「構造的暴力の縮図」であり、階級闘争と国際連帯を考えるうえで決定的に重要なテーマとなります。
① 「民族絶滅」としての植民地支配
イギリスによるアイルランド支配を、単なる経済的搾取ではなく、アイルランド人を民族的に消去する運動として位置づけることができます。これは現代で言う「エスニック・クレンジング(民族浄化)」に近い視点です。
アイルランドの土地は、イギリス人地主によって収奪され、文化や言語は「未開」とされ、政治的自治は1801年の合邦によって封じられ、労働力は移民として国外に追い出され、残された者たちは貧困にあえぎながら、プロテスタント地主層の下で従属する。
つまりアイルランド支配とは、「人々を生かしたまま民族としての存在を剥奪する」構造であり、これは資本主義の拡張がもたらす根源的な暴力のひとつです。
② 合邦と「封印」されたもう一つの近代
アイルランドは18世紀末から共和主義・自由主義の思想に開かれた可能性を評価できます。とりわけ、アメリカ独立やフランス革命の影響下でアイルランドが選び得たはずの近代化の道に注目していたのです。
ところが、1801年の「連合法(Act of Union)」により、イギリスはアイルランドの議会を解体し、形式的に「合邦」することで、この別の可能性を封じ込めます。
これは、ナポレオン戦争期の軍事的・政治的な防衛措置であると同時に、アイルランドを自立的近代化から意図的に引き離す操作でもありました。
ここに「歴史の封印」を見ています。アイルランドは独自の近代を歩むことを禁じられ、イギリス資本主義の後背地、つまり周辺として位置づけられるようになるわけです。
周辺化された「農業的後背地」としてのアイルランド
アイルランドはイギリス資本主義の発展の“犠牲者”です。産業革命が進むイギリス本土に対して、アイルランドは農業依存・未工業化の「供給地」として位置づけられ、意図的に発展を妨げられたのです。
これは、後の「世界システム論」(イマニュエル・ウォーラーステインなど)で展開されるような、
- 中心=イギリス(産業・資本)
- 周辺=アイルランド(農業・労働力供給)
という経済的分業構造そのものであり、資本主義の発展がすべての地域に恩恵をもたらすわけではないという洞察の先駆けでもあります。
④ 労働者階級の分断と連帯の障害
アイルランド人の移民労働者は、イギリスの労働者階級の中でもっとも過酷な労働と差別にさらされていました。イギリス人労働者の多くは、アイルランド人を「賃金を引き下げる競争者」として忌み嫌い、敵意と軽蔑の対象としていました。
資本主義で有名なマルクスの考えを応用するなら、この「労働者階級内部の分断こそが、ブルジョワジーの支配を可能にしている構造的要因」があります。
つまり、イギリスとアイルランドの対立を放置したままでは、国際的な労働者の連帯(インターナショナリズム)は決して実現しないのです。