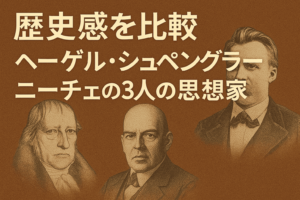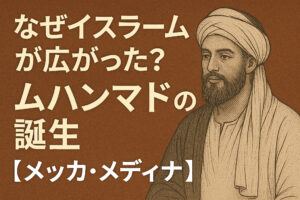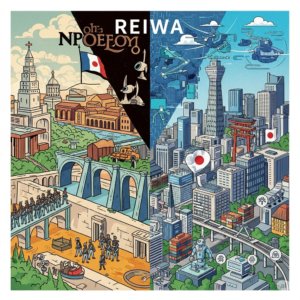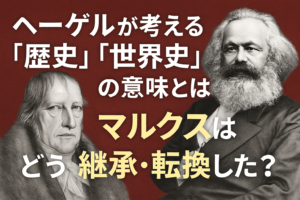「文明は豊かな自然から生まれた」と、私たちはなんとなく思い込んでいないでしょうか。
しかし実際にはその逆。人類史における大きな飛躍――文明の発祥をもたらしたのは、じつは地球規模の「乾燥化」だったのです。
約5000年前、サハラをはじめとする広大な地域が緑豊かな大地から砂漠へと変わり、人々は水源を求めて大河のほとりに集まりました。そこで農業が始まり、水を分け合い管理する仕組みが必要になり、やがて都市と国家が誕生しました。
つまり「恵まれた自然」ではなく、「厳しい環境こそが文明を生んだ」と言えるのです。
本記事では、「乾燥化と文明発祥」というあまり語られない視点から、私たちが暮らす社会の起源をひも解いていきます。
まず結論→文明・都市・集住の因果連鎖
気候変動(乾燥化)
↓
水辺への定住(生存のため)
↓
農業・灌漑の必要性
↓
人の集中・分業・協働
↓
制度化・技術の発展
↓
都市と文明の誕生
乾燥化から文明発展までの流れ
文明が発祥した地域、いわゆる四大文明(メソポタミア、エジプト、インダス、中国)の成立時期、つまり紀元前5000年〜前2000年頃、地球規模で気候の乾燥化が進行していました。
乾燥化が進む中で、人々は水源を求めて川のほとりに集まりました。定住が進むと、耕作や灌漑の必要性が生まれ、水の管理が集団的に行われるようになります。これがやがて共同体の形成、技術の発展、権力の集中へとつながり、都市や国家、そして文明の萌芽へと発展していきました。
実際、紀元前5000年頃から、アフリカ北部〜中東〜中央アジア〜中国に至る一帯で、地球規模の乾燥化が始まりました。この気候変動のインパクトは非常に大きく、世界の主要な文明の多くがこのラインに沿って誕生している事実と呼応しています。
特に象徴的なのがサハラ砂漠です。現在では想像もつきませんが、この地はかつて「グリーンサハラ」と呼ばれるほど、緑豊かな湿潤地帯でした。動植物も豊かで、人々は狩猟や採集を通じて暮らしていたと考えられています。
サハラ砂漠のタッシリ・ナジェールの洞窟壁画には、当時の湿潤なサハラで人々が牧畜や農耕、日常生活を営む姿が生き生きと描かれています。現在の砂と岩の荒涼とした風景からは想像しがたいですが、これらの壁画が気候変動と人類の生活の劇的な変化を物語っています。
ところが、前5000年ごろから急速に乾燥が進行し、次第に遊牧や採集生活が成り立たなくなっていきます。人々は水のある場所へと移動し、河川沿いに定住するようになりました。こうして生まれたのが、ナイル川、チグリス・ユーフラテス川、インダス川、黄河といった大河流域における初期文明です。
文明は「恵まれた環境」ではなく、「厳しい環境」から生まれる
文明の発祥において、乾燥化が重要な役割を果たしたのはなぜか——
それは、水という限られた資源をどう活用するかに、人々が知恵を絞るようになったからです。
乾燥化が進む中で、人々は水源を求めて川のほとりに集まりました。定住が進むと、耕作や灌漑の必要性が生まれ、水の管理が集団的に行われるようになります。これがやがて共同体の形成、技術の発展、権力の集中へとつながり、都市や国家、そして文明の萌芽へと発展していきました。
文明は「自然に恵まれた場所」で自然発生的に生まれたのではなく、環境的に恵まれなくなったことで、人類が生き延びるために創意工夫を重ねた結果として生まれたと言っても過言ではありません。
逆説的ですが、困難な環境こそが、人類の創造性と社会構築力を引き出したのです。
なぜ日本では文明が発祥しなかったのか?
文明の発祥には、水の枯渇=乾燥化が重要な契機となります。乾燥化が進行するなかで、人々は水源に集まり、水を効率よく使う方法を模索する必要に迫られました。これが灌漑・治水技術、政治制度、分業体制、文字や記録の発明といった文明の基本要素を生み出す原動力となったのです。
ところが日本列島は、次のような条件により、このような「文明誕生の圧力」が存在しませんでした。
日本に文明が発祥しなかった3つの理由
- 乾燥化が起きなかった
日本は湿潤なモンスーン気候に属し、安定して豊富な降水がありました。極端な水不足が起こらず、「水をめぐる生存競争」が必要なかったのです。 - 自然環境が豊かすぎた
森・川・海が身近にあり、食料採集・狩猟・漁労で十分に生活が成り立ちました。これは縄文文化が1万年以上続いたことからも明らかです。
結果として、人々が「大規模に農耕し、集住し、労働を分業し、社会を統治する」必要性が薄かったのです。 - 水の活用システムを構築する動機がなかった
ナイル川や黄河のように「水を制する者が社会を制する」という状況が日本では生まれませんでした。水はどこにでもあり、誰のものでもなかったため、水利管理を中心に人々が組織されることがなかったのです。
文明とは、「豊かな自然に恵まれた結果」ではなく、むしろ「環境的制約を乗り越えるための知恵の結晶」です。
その点で言えば、日本はあまりに自然に恵まれすぎていた――つまり「文明が生まれる必要がなかった」地域だと言えます。
重要論点まとめ
1. なぜ文明が生まれたのか?
文明は、人類が自然環境の変化(特に乾燥化)に適応しようとする過程で生まれました。
具体的には、気候が乾燥し、従来のような移動型の狩猟・採集生活が困難になると、人々は水源のある地域(大河の流域)に定住せざるを得なくなりました。定住すると人口が増え、食糧の安定供給(農業)、資源の管理、治水・灌漑、秩序の維持などが必要になります。
これらの課題を解決する中で、技術・制度・文字・宗教・階級といった文明の構成要素が形成されていったのです。
2. なぜ文明は都市と結びついているのか?
都市とは、人々が集住し、機能分化(分業)し、社会制度が高度に組織された空間です。
文明が成立するには、ただ人が集まるだけでなく、農業生産を支えるインフラ、労働の分業、秩序を保つ政治的仕組み、情報を蓄積する文字や記録手段などが必要でした。これらの要素がまとまって機能するのが都市であり、したがって文明の発祥は都市の発展と不可分なのです。
3. なぜ都市は生まれたのか?
都市の起源は、農業の発展と定住にあります。
農業によって食糧が安定的に得られるようになると、狩猟採集社会に比べてより多くの人口を養うことが可能になり、同時に人々は同じ場所にとどまる理由を持つようになります。
また、農業には共同での水利管理や労働の調整が必要なため、自然に人が集まり、協力関係が制度化されていきました。やがてこれが恒常的な集住(村)となり、やがて政治的・宗教的中心を持つ都市へと発展します。
4. なぜ人々は一カ所に集まったのか?
その大きな理由は、「生き延びるため」です。
乾燥化によって水と食料の確保が難しくなるなか、人々は水源に依存せざるを得なくなり、水辺に集中しました。加えて、農業や灌漑には多人数での協働作業が不可欠であり、また生産物の蓄積や分配、外敵からの防衛のためにも集まることが合理的でした。