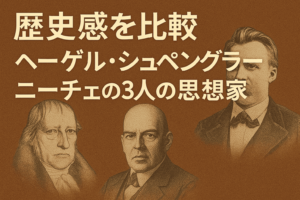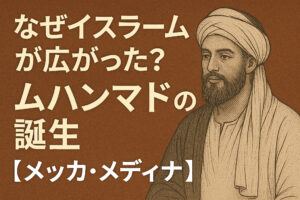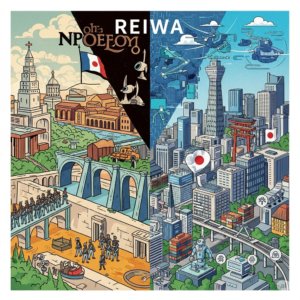ナポレオンの軍靴の音、ウィーン会議で踊り続ける外交官たち、ビスマルクが鉄と血の演説で国を動かした瞬間――18世紀から19世紀のヨーロッパ史の主役たちは、いつもスポットライトを浴びてきました。
でも、そのきらびやかな舞台の裏で、“静かに、でも確実に”勢力を広げた国があるんです。それが、今日の主役、ロシア帝国です。
当時、北欧の覇者だったスウェーデンと、東ヨーロッパの大国だったポーランド=リトアニア共和国は、偶然にも同じ時期に国力が衰えていきました。ロシアは、まさにこの“スキマ”を見つけて、バルト海や東ヨーロッパへとじわじわと勢力を広げていったんです。
さらに驚くべきことに、ロシアはプロイセンという、最初は小さな国だった“同盟相手”を育て上げ、それがやがてドイツ統一の陰の立役者となるんです。あのカール・マルクスですら、この時代に「ヨーロッパの鍵はロシアだ」と見抜いていたんですよ。
この記事では、ロシアが近代ヨーロッパの秩序を大きく変える“ピボット”(中心軸)になった仕組みを、7つのステップで解き明かしていきます。読み終わる頃には、ドイツ統一も、普仏戦争も、そして第一次世界大戦までが、まるで一本の線でつながったように見えてくるはずです。
キーワード:ロシア帝国, ポーランド分割, プロイセン, スウェーデン, ウィーン体制, マルクス史観, 第一次世界大戦への伏線
読みどころ: スウェーデンとポーランドの“谷間”に潜り込み拡張したロシアの長期戦略と、それを軸に連鎖したプロイセン台頭〜ドイツ統一、そして第一次世界大戦前夜までを一気通貫で把握します。
結論を先出し!
簡単な流れcheck!
- スウェーデン(北欧の覇者)と ポーランド=リトアニア(中東欧の大国)が同時期に衰退
- その“間隙”にロシアがバルト海と東欧へじわりと浸透
- プロイセンという“小さな同盟相手”を育て、やがてドイツ統一の黒幕に
- マルクスは早くから「ヨーロッパの鍵はロシアだ」と喝破
18世紀から19世紀にかけて、ロシア帝国はヨーロッパの表舞台ではあまり目立たない存在でしたが、その「縁」(フチ)の地域で着実に影響力を広げ、結果としてヨーロッパ全体の力のバランスを大きく変えました。
- 北欧の縁: スウェーデンを衰退させ、フィンランドを併合することでバルト海の安定を手に入れ、その後のロシア海軍力強化の土台を築きました。
- 東欧の縁: ポーランドを分割することで、西ヨーロッパへの進出ルートを確保し、戦略的に有利な位置を得ました。
- 中欧の縁: 小さな国だったプロイセンを育て上げ、オーストリアをけん制することで、間接的にドイツ統一を後押しし、新しい強国が生まれることに深く関わりました。
- 南東欧の縁: バルカン半島でスラヴ民族の保護を掲げ、主要国間の不信感を最大限に高め、第一次世界大戦の遠い原因を作り出しました。
 たかりょー
たかりょーロシアは、自国の安全を守り、勢力圏を広げるというはっきりとした国家目標のために、時には巧みな外交交渉を使い、時には軍事力を背景に、ヨーロッパの“縁”の部分を支配していきました。その結果、ロシアは単なる東の辺境の国から、ヨーロッパの運命を左右する「縁の支配者」へと大きく変わったのです。
視点1:スウェーデンが弱った瞬間、ロシアが北欧をゴッソリいただく
1-1大北方戦争(1700〜1721)
17世紀の終わり頃、スウェーデンは「北方のライオン」と呼ばれるほどむちゃくちゃ強い国でした。三十年戦争(1618–1648)では新教側の英雄グスタフ・アドルフが活躍し、一時はバルト海の覇者として「バルト帝国」を築き上げています。
でも、そのスウェーデンにデンマークとサクセン、そして新しく力をつけ始めたロシアがケンカを仕掛けたのが、大北方戦争です。この戦争は、当時のヨーロッパの勢力図を大きく変えるきっかけとなりました。
この戦争で一番のポイントは、1709年のポルタヴァの戦い!この戦いは、1709年7月8日(露暦6月27日)に、北方戦争中にウクライナのポルタヴァで行われました。
スウェーデン国王カール12世は、勇敢な指導者として知られていましたが、ピョートル大帝率いるはるかに数の多いロシア軍に大敗してしまいます。カール12世はオスマン帝国に逃げ込むことになり、これでスウェーデンの北欧での覇権は瓦解。支配力は事実上終わりました。
この敗北によって、北欧のパワーバランスはガラリと変わり、ロシアが新しい強国として頭角を現す土台ができたのです。



ピョートル大帝が「北方のライオン」カール12世を撃破。ポルタヴァの戦い(1709)が決定打!
1-2サンクトペテルブルク建設(1703〜1721)=西欧への“窓”
大北方戦争が終わる前の1703年、ピョートル大帝は、バルト海のネヴァ川の河口にある湿地に、新都サンクトペテルブルクの建設を始めました。そして、大北方戦争が終わった1721年のニスタット条約で、正式に首都をここに移すことが決まります。
正直、「こんなドロドロの場所に首都!?」って思いますよね(笑)。でも、彼は本気でロシアを「西欧への窓」にしようとしていたんです。
ピョートル大帝は、バルト海の制海権(海の支配権・海の通行券みたいなもの)を手に入れ、同時に西ヨーロッパの文化や技術を積極的に取り入れようとしました。これは、軍事力強化(ハード)と文化導入(ソフト)を同時に狙った、まさに“ハード+ソフト”戦略だったんです。サンクトペテルブルクは、ロシアが西ヨーロッパに開かれた“窓”となり、ロシアがヨーロッパの主要国の一つとして認められるための大切な一歩となりました。



湿地に首都を移すとか普通やらんよね?でも「西欧への窓」を本気で開けたかったらしい。
1-3フィンランド併合(1809)=“緩衝地帯づくり”の教科書例。氷と海で北側はほぼ鉄壁に。
スウェーデンの力が衰えた後も、ロシアは北欧での影響力を着実に広げました。
エカチェリーナ2世の時代にもスウェーデンとの戦争は続き、最終的にはアレクサンドル1世の時代、1809年にフィンランドを大公国(ロシア帝国の支配下にある自治領)として併合しました。
このフィンランド併合は、ロシアが“緩衝地帯”(敵からの攻撃を和らげるための土地)を作る典型的な例です。
つまりロシア本土とスウェーデンの間に、バルト海とフィンランドの土地を挟むことで、スウェーデンが再び攻めてくるのを長期的に防ぐ狙いがありました。ロシアは、征服した地域に対して「征服はするけれど、ある程度の自治は認める」という方法を取りました。これにより、もし反乱が起きても、首都からは遠い場所なので対応しやすく、北欧地域をロシアの支配下にしっかりと組み込むことに成功したのです。



【僕の学び】
「征服+自治」の合わせ技で、遠い地方=スウェーデンを“おとなしく”させるの上手すぎ。フィンランドに自治を認めることで、わざわざ兵隊を置いて監視しなくても、反乱が起きにくいようにしてたってことですよね。頭いいなぁ。
視点2:ポーランド=リトアニアを3回に分けて消し去る
2-1 ポーランド=リトアニア共和国の“内なる崩壊”
次にロシアが狙ったのが、東ヨーロッパの大国、ポーランド=リトアニア共和国です。スウェーデンと同じように、18世紀のポーランド=リトアニア共和国もまた、国の内側から崩壊が進んでいました。
この国が弱かった理由の一つに、「リベルム・ヴェト」(Liberum Veto)っていう制度がありました。これは、議会でたった一人の議員が反対するだけで、すべての議案が否決され、議会そのものが解散させられてしまうというものでした。
この制度は、もともと国王の力を制限し、貴族たちの自由を守るためのものでしたが、結果的には国が大切なことを決められない状態が続き、外国の介入を招く原因となってしまいました。
国王の座をめぐる貴族たちの争いも絶えず、隣接するロシア、プロイセン、オーストリアは、この混乱を「仲裁」と称して介入し、自分たちの利益を追求していったのです。
■ ポーランド=リトアニア共和国衰退の理由まとめ
- 強力な中央権力が育たず、分裂的な貴族支配
- 外交・軍事の決定が困難となり、周辺国に対して脆弱に
- 17世紀後半〜18世紀にかけてロシア、プロイセン、オーストリアに領土を分割され、18世紀末には消滅(ポーランド分割)
2-2 ポーランド=リトアニア共和国の三度の分割:エカチェリーナ2世の外交傑作



ポーランドがこんな状態だったので、隣のロシア、プロイセン、オーストリアの三つの強国が、「俺たちが仲裁してやるよ〜」って顔で、ポーランドの領土を自分たちで分け合うという、とんでもないことを3回もやりました。これがポーランド分割です。
ポーランドの弱体化と周辺の強国の介入は、最終的にポーランド=リトアニア共和国の悲しい運命を決定づけました。
三度行われたポーランド分割(1772年、1793年、1795年)は、エカチェリーナ2世が治めていたロシアが主導し、プロイセン、オーストリアと協力して行われた、まさに「外交の傑作」とも言えるものでした。
| 年 | ロシアが手に入れた土地 | プロイセンが手に入れた土地 | オーストリアが手に入れた土地 |
| 1772 | 現在のベラルーシ東部 | バルト海につながる回廊 | ガリツィア地方(豊かな穀倉地帯) |
| 1793 | ベラルーシ西部とウクライナのドニエプル川右岸 | ポズナン地方 | – |
| 1795 | ワルシャワ周辺を含むポーランドの中心部とリトアニアの一部 | マゾフシェ地方北部 | クラクフ周辺 |
この分割によって、ポーランド=リトアニア共和国はヨーロッパの地図上から消滅しました。ロシアは広大な土地を手に入れ、西ヨーロッパへの進出ルートを確保しました。
2-3 ポーランドが地図から消滅 → “ポーランド問題”がヨーロッパの火種に
結果、ポーランドはヨーロッパの地図から完全に消えてしまいました。ロシアはこれで、西ヨーロッパへの道を手に入れ、さらに力をつけました。将来フランスからの干渉やドイツ統一といった西からの脅威を遠くから抑えるという、重要な戦略目標を達成しました。
「国が地図から消える」という出来事は、当時の強国たちに「力の論理」という、冷たい現実を再認識させました。国際秩序が、もはや伝統的な正義や法律ではなく、国の実力によって決まる時代が来たことをはっきりと示唆したのです。
ポーランドの人々は、国を失っても独立への強い願いを持ち続けました。1830年や1863年に起きたポーランドでの独立を求める反乱は、ヨーロッパ各地で盛り上がっていた自由を求める運動と結びつき、国際的な注目を集めました。この「ポーランド問題」は、その後の国際政治における不安定な要素となり続けます。
視点3: 小国プロイセンを“ロシア製・準強国”にブースト
3-1 小国プロイセン、なぜ伸びた?
18世紀の初め頃まで、ブランデンブルク=プロイセンという国は、決して大きな国ではありませんでした。しかし、この小さな王国は、ポーランド分割をきっかけに急速に力をつけていきます。ポーランド分割によって、プロイセンは工業に必要な資源やたくさんの人々を「爆買い」するような形で手に入れ、国の経済基盤を強くしました。
さらに、プロイセンが成長できた大きな理由の一つに、ロシアからの積極的な支援があります。ロシアは、スウェーデンをけん制するための最前線として、プロイセンに軍事的な資金や政治的な後押しを与えました。両国は、時には協力し合い、時にはけん制し合いながらも、お互いがお互いを必要とする関係を築いていったのです。
3-2 ティルジット条約(1807)と“裏切りのバランス”
ナポレオン戦争中、プロイセンは1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いでナポレオン軍に大敗し、国が滅びるかもしれないという危機に陥りました。この時、プロイセンを救ったのはロシアでした。1807年のティルジット条約では、ロシアがプロイセンの領土がこれ以上削られないように尽力し、その代わりに、フランスがイギリスに行っていた大陸封鎖令(イギリスとの貿易を禁止する命令)に協力することを約束しました。
この条約は、ロシアとプロイセンが、お互いを「都合のいい時だけ利用する同盟相手」と認識しつつも、ヨーロッパ全体の力の均衡(バランス)を保つために利用し合った典型的な例です。ナポレオンが失脚した後のウィーン体制(ナポレオン戦争後のヨーロッパの秩序)のもとでは、両国はさらに接近し、ヨーロッパの秩序を守るための協力関係を深めていきました。
3-3 オーストリア vs プロイセン:ロシアは高みの見物で“漁夫の利”
19世紀に入ると、ドイツ統一をめぐって、オーストリアとプロイセンが激しく対立するようになります。多民族国家であるオーストリアは、国内に多くの民族問題を抱え、その国力は相対的に停滞していました。一方、ロシアは、バルカン半島(東南ヨーロッパ)での自由な行動を得るために、中央ヨーロッパの「警察役」をプロイセンに任せるという、とても巧妙な戦略を取りました。
その結果、プロイセンは「ロシアに育てられた準強国」として力をつけ、やがてドイツ統一の中心を担うことになります。ロシアは、このオーストリアとプロイセンの対立を静かに見守ることで、自分の影響力をドイツの地域に広げることに成功したのです。
視点4: 大ドイツ vs 小ドイツ:統一をめぐる兄弟喧嘩
19世紀半ば、ドイツを一つにまとめることは、とても大切な課題となっていました。そして、その中心になるのはどちらの国か、ということで、オーストリアとプロイセンが激しく争いました。
| 立場 | 主導する国 | 目指した統一の形 | 準備段階 | 結末 |
| 大ドイツ主義 | オーストリア | ドイツ語を話すすべての地域と、オーストリアの多民族を含めて、ハプスブルク家が束ねる | 1848年のフランクフルト国民議会(ドイツ全体で憲法を決めようとした会議) | 普墺戦争で失敗に終わる |
| 小ドイツ主義 | プロイセン | オーストリアを除外し、北ドイツを中心に統一する | 関税同盟(経済的な協力)から北ドイツ連邦(政治的な連合)へ | ドイツ帝国として統一される(1871年) |
普墺戦争(1866年)では、ロシアは「友好的な中立」を宣言しました。つまり、どちらの味方もせず、でもプロイセンにとって有利になるような態度を取ったのです。このロシアの姿勢が、プロイセンの勝利を決定づける要因の一つとなりました。プロイセンが勝ったことで、「ロシアの保護国ネットワーク」が中央ヨーロッパに広がり、ドイツ地域におけるロシアの影響力はさらに強固なものとなりました。
次に起こった普仏戦争(1870–71年)でも、ロシアは静かに状況を見守っていました。これは、クリミア戦争(1853-1856)で失った黒海艦隊を再建することをビスマルクと秘密裏に約束していたためです。ロシアがフランスへのけん制を保証したことで、ビスマルクは安心してフランスとの戦争に集中でき、その結果、プロイセンを中心にドイツ帝国が誕生することになります。
視点5. 1850〜60年代:列強と“準列強”の国際的布置
19世紀の半ば、ヨーロッパは、「強国」と「準強国」の間で、複雑な力のバランスが保たれていました。
この時代、力が衰えつつあった国としては、国内に多くの民族問題を抱え、産業化が進まなかったオーストリアが挙げられます。
一方、力をつけ始めていた国としては、軍事改革を進め、ロシアの支援を受けていたプロイセン、そしてイタリア統一を進めていたサルデーニャ王国(後のイタリア)がありました。
この国際関係の中で、ロシアがどちらの勢力に味方するかによって、フランス、イギリス、ドイツ圏のバランスが大きく変わる、という状況でした。
ナポレオン戦争後のウィーン体制が揺らぎ始め、東ヨーロッパやドイツの地域は、まるで「力の真空地帯」になりつつありました。カール・マルクスがこの頃に「反革命の司令塔であるロシア」を厳しく批判したのは、このような不安定な国際情勢があったからなのです。
- 衰退国: オーストリア(民族摩擦と産業化停滞)
- 上昇国: プロイセン(軍事改革+ロシア後援)、イタリア諸国(サルデーニャ)
- バランス: ロシアがどちら側に傾くかで、フランス・イギリス・ドイツ圏の三角形が変形
視点6:マルクスが見抜いた「ヨーロッパのカギ」ロシア
カール・マルクスは、当時のヨーロッパ政治の本当の中心にロシアがあることを鋭く見抜いていました。彼は『ニューヨーク・デイリー・トリビューン』という新聞に1854年に書いた記事で、「ロシアの専制政治(皇帝が絶対的な力を持つ政治)がある限り、ポーランドも、ドイツも、スカンディナビア諸国も、本当の自由を得ることはできない」と断言しています。
6-1 “反革命”の双柱:オーストリアとロシア
1848年、ヨーロッパ各地で革命の嵐が吹き荒れた時、オーストリア皇帝は、ハンガリーでの反乱を鎮めるためにロシア軍に助けを求めました。ロシアはこれに応じ、見事に反乱を鎮圧しました。この成功体験は、ヨーロッパの自由を求める人々に「革命を起こしても、ロシアにつぶされる」というトラウマを深く刻み込みました。これにより、ロシアが「反革命の二大柱」(もう一つはオーストリア)の一つであることをはっきりと示したのです。
6-2 ロシアが動けばパズルが崩れる
マルクスは、ロシアの外交的な動きが、ヨーロッパ全体の力のバランスに与える影響の大きさを指摘しました。
- プロイセンを支援する: ドイツ統一が加速し、フランスを囲い込むような同盟関係が作られる。
- フランスに近づく: オーストリアが孤立し、イタリア統一が進む。
- クリミア半島から南へ進出する: イギリスとフランスが同盟を結び、東地中海地域での「グレートゲーム」(大国同士の勢力争い)へと発展する。
このように、ロシアのちょっとした動き一つ一つが、ヨーロッパ全体の外交的な「パズル」を大きく崩してしまう引き金になりうることを、マルクスは鋭く見抜いていました。
6-3 “ポーランド問題”こそ回路ブレーカー
マルクスが特に重要視したのは「ポーランド問題」でした。ポーランドで独立を求める反乱が起きるたびに、ロシアは大きな軍隊を動かし、そのたびにヨーロッパ全体に緊張が走りました。
マルクスは「ポーランドの解放なしには、ヨーロッパの解放もない」と繰り返し主張し、ポーランドの独立が、ロシアの専制政治を打ち破り、ひいてはヨーロッパ全体の自由を実現するための鍵であると考えたのです。
視点7:バルカンの火薬庫と第一次世界大戦への伏線
19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、ヨーロッパの緊張は、まるで爆発寸前のバルカン半島へと集中していきます。ロシアは、この地域に住むスラヴ民族の保護者を宣言し、セルビアやブルガリアで汎スラヴ主義運動(すべてのスラヴ民族が団結しようとする動き)をあおりました。これは、弱体化するオスマン帝国に乗じて、ロシアが黒海から地中海へ進出する、長年の戦略の一部でもありました。
このロシアの動きに、オーストリアは強く反発し、1908年にはボスニア・ヘルツェゴビナの併合を力ずくで行います。これにより、バルカン半島におけるロシアとオーストリアの対立は決定的となり、ヨーロッパの主要国間の緊張は一気に高まりました。
こうした状況の中で、フランスとロシアは1894年に仏露同盟を結び、さらにイギリスとフランスは1904年に英仏協商を結びました。これら一連の動きは、やがて三国協商という同盟関係へとつながり、ドイツはヨーロッパの主要国に囲まれているという強い危機感を抱き、軍備増強(軍拡)を加速させることになります。
そして1914年、サラエヴォ事件が発生すると、ロシアはスラヴ民族の盟主としてセルビアを支持することを表明し、軍隊の動員令を出します。これに対し、ドイツはロシアに宣戦布告を行い、ヨーロッパ全体は第一次世界大戦という、かつてないほどの大きな破局へと突き進んでいったのです。